皆さんは日々のタスクの優先順位を、どのように決めているでしょうか。
私は現役で商社の営業マンをしています。周りにいる営業を見ていると、営業成績とタスクの優先順位の決め方は、ある一定の相関があることに気が付きます。
自分が設定した期限を優先して仕事をしている人は営業成績が低い傾向があり、取引先目線で仕事をしている人は営業成績が高い傾向がある。
そんな当たり前な法則ですが、どちらも営業に聞くと「取引先を最優先に行なっている」と言います。この違いは何でしょうか。
今回はタスクの優先順位の決め方や、優先順位が高いものと低いもの、それぞれの対応方法をご紹介します。

- 労働時間の割に営業成績が追いついていない人
- 返報性の原理やエッセンシャル思考などの、営業の戦術に興味がある人
 新野くん
新野くんいきなり取引先から電話かかってきて、今日中に対応して欲しいってきたよ〜、、まだ1週間前のメールすら処理してないのに。
 くろひつじ
くろひつじメン!営業やってるね〜。取引先だって営業が忙しいのはわかってるんだ。そのうえで電話がくるってことはトラブルかな?
結論から先に言うと、営業が優先すべきはトラブル対応です。有事の依頼は取引先からの期待値が最も高いタスクであり、求められている動きをすれば最短で信頼が構築できます。
ある一部の営業には、トラブル対応しかしない(日々のメールは一切見ない)人もいます。重要なメールは後々トラブルへと発展しますが、その対応が早く正確なのです。
これは極端な例ではありますが、しかし彼は取引先からの信頼が非常に厚く、一方で日常のタスクを優先する営業は労働時間が肥大化し、それに見合う結果は出していません。
限られた時間の中で結果を出すためには、優先順位の低いタスクは自分で排除する必要があるのです。
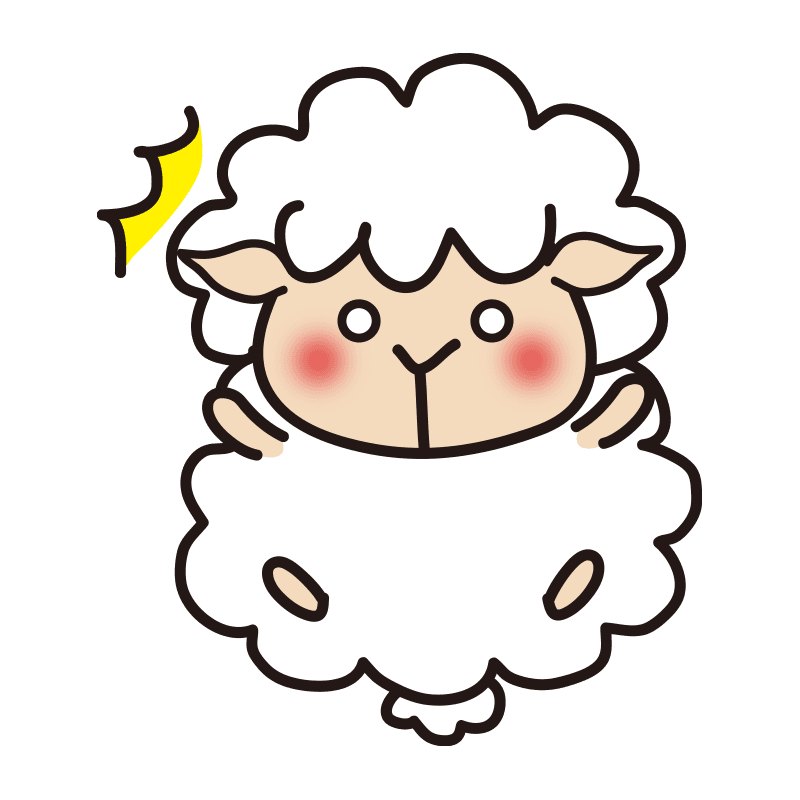
- 営業にとって有効な戦術は返報性の原理とエッセンシャル思考である。
- 思考面で重要なのは、営業の役割を曖昧にせず批判と愚痴を明確に分けること。
- 行動面で重要なのは、有事において顧客の期待と自分の行動を同一にすること。
トラブル対応が重要な理由

ビジネスの現場におけるタスクは、事前に予測できるものと、予測できないものに分類できます。
- 予測できるタスク:資料作成、打ち合わせ、社内業務(エントリー、注文書発行、売上)など
- 予測できないタスク:電話、メール、トラブル対応など
特に営業は、他の職種と比べ予測不能なタスクの比重が高いため、すべてのタスクに優先順位を割り振ることが求められます。
もし皆さんの周りに営業成績が高く取引先からの信頼が厚い人がいるならば、その人は優先順位の割り振りが早く正確であると言えます。
優先順位の「正確」
営業の役割は、顧客を知り信頼を獲得することです。この信頼を獲得するためには、営業にとって取引先がどれだけ重要な存在かを、行動で示す必要があります。その最も効果的な手段が、トラブル対応時の「正確」さです。
優先順位の「正確」とは、取引先が期待しているタスクの優先順位が、営業の動きと同一であるかで決まります。
営業の役割については以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

返報性の原理
営業はよく返報性の原理を利用しており、常識的な相手に対しては、より恩を売れる方を判断し選択しています。

返報性の原理とは、主に営業やマーケティングの分野で用いられる考え方で、人は「何かをしてもらったら、お返しをしなければならない」と思う心理的な仕組みを指します。人間は社会を形成していく進化の過程でこの仕組みを会得しており、無料の試食会やティッシュ配りなどで活用されています。
目的はもちろん、相手が最も恩を感じる選択をすることですが、その行動に最も適している環境がトラブル状況下です。有事の際、取引先は以下のような不安に駆られています。
- 営業が対応してくれなければ上司に怒られる。
- 営業が対応してくれなければ商品を購入できない。
- 営業が対応してくれなければ納期の把握ができない。
人間は何かを手にするより、何かを失うことにより恐怖する生物です。ここで求められた動きをすることが、信頼を獲得する最も手軽な方法なのです。
エッセンシャル思考
エッセンシャル思考とは、「より少なく、しかしより良く」を目指す思考法です。自分にとって本当に重要なことだけに集中し、他を捨てることでより大きな成果を上げることができます。
根拠
代表的な根拠は、「パレートの法則(別名:8対2の法則)」です。パレートの法則とは「全体の成果の約80%は、20%の原因から生まれる」法則を指します。
具体的な行動
結果の出た行動は洗い出しが難しいため、まずは重要でないタスクをリスト化し、「やらないことリスト」を作成します。
日々のメールや電話などの予測できないタスクの中で、不急不要な事柄はないでしょうか。その依頼に答えた結果、よりタスクが増えてしまったことはないでしょうか。
労働時間だけが肥大化している人は、改めて重要でない事柄について考える時間を設けましょう。
トラブルの種類

営業をしていると、トラブルに対応する頻度は決して少なくありません。本章では、その代表的な事例と対応方法をご紹介します。
緊急性が最も高いトラブル
緊急性が高いものとは、例えば生産設備の場合はバグによりラインが停止。また部品や食品の場合は不良によりエンドユーザーからクレームが入ったケースなどがあります。
この状況では、まずサプライヤーにいち早く情報を共有し、最短で状況確認を行います。確認後は不具合やバグの解消。必要に応じて顛末書の作成を行い、経緯と問題点について顧客へ説明します。
とにかくスピードと正確さが重要であり、自社の存亡を賭けたタスクとなるため、他の事柄は置き去りにして構いません。
検収時のトラブル
検収とは一般に納品物を受け取ることを指しますが、営業の間では支払いの意味も持ちます。顧客への納品を終えたら、要求仕様や検収条件を満たしているか、顧客との打ち合わせにて最終チェックを行います。
そこで検収条件を満たしている場合には無事検収されますが、もし満たしていない場合には満たすまで検収されません。
顧客が避けたいリスク
- 検収条件を満たし商品も使用できるが、取引先から使途不明の追加請求がきた。
- 検収条件を満たさない要因が曖昧で、下請法上先に支払いをしなければならない。
- 先に支払いをした結果、取引先が対応しなくなり、商品を使用できる状況ではなくなった。

下請法(正式名:下請代金支払遅延等防止法)とは、不当な値引きや返品の強要、支払い遅延などを防止する法律です。下請が発注会社より資本金が少ない場合に適用されます。
この検収条件のトラブルは日常茶飯事で起きます。営業によっては、ここで顧客に対してサプライヤーと同じ文言をぶつける人がいますが、そのような方は営業である資格はありません。
自社が商社などの仲介業者であれば、サプライヤーへ支払いを終えさっさと追加費用を注文しましょう。そこで顧客と交渉するのは時間を無駄にするばかりか、顧客からの信頼を損なう悪手です。
営業が交渉を行う場面は、以下のような営業がコントロールできないトラブルに限定されます。
- リピート品の見積もりが実績値より値上がりした。
- 発注後もしくは設計・制作中にトラブルがあり設定納期が変更になった。
優先順位の低いタスクの処理方法

優先順位の低いタスクとは、トラブルに該当しないもの全般を指しますが、タスクの分類により対応方法が異なります。
即応するもの
- スケジュールに関連するもの(打ち合わせ日程など)
- 期限付きの依頼
スケジュール関連は営業だけでなく取引先の予定にも影響するため、即応しましょう。このようなタスクは答えが決まっており、調整が終われば長引くことはありません。
また期限付きの依頼は取引先からの信頼に直結します。早めに手を付け進捗報告をすることで、タスクの完成度を高め、顧客を安心させることができます。
対応しないもの
- 注文が決まった後のQ&A
- 社内業務(エントリー、注文書発行、売上)
営業の役割は顧客を知り信頼を獲得することであり、この役割とは逸脱したタスクはやる必要はありません。
例えば商品に関するQ&Aは社内の技術者、またはサプライヤーの方が詳しいです。直接連絡を取ってもらうか、メールであればCC:に入れましょう。
社内業務に関しても、事務やアシスタントに任せれば良いです。会社によっては「営業がやるものだ」と考えている場合がありますが、そのような会社は早々に立ち去ることをお勧めします。
意識すること
- 営業の役割を曖昧にしない
- 批判と愚痴を明確に分ける
顧客から信頼を獲得することは、決して容易なことではありません。信頼とは感情であり、相応の時間を投下する必要があります。
自分の役割に集中しましょう。あれもこれも営業が対応しようとすると、会社組織におけるそれぞれの役割が分散されタスクが曖昧になります。
それが理解できない人からは陰口を言われることもありますが、社内からの愚痴は気にする必要はありません。取引先からの批判は真摯に受け止める必要はありますが、愚痴は良いネタになります。
最後に
今回はタスクの優先順位の決め方や、優先順位が高いものと低いもの、それぞれの対応方法をご紹介しました。
営業の世界では、上司から「自分を持て」と言われる機会が多々あります。これは「自身の強みを認識し、やらない事を決めよ」と言う意味を持ちます。自身の強みが曖昧な人は、これを役割と言い換えても良いです。
顧客からの信頼を獲得した要因は明確な理由付けが難しく、自身の強みを言語化しにくい分野です。しかし、そこには必ず強み(理由)が存在します。その強みに付随しないタスクは他へ振るという意識をしましょう。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。




