現代は物流の進歩により、海外から商品を購入するのが容易になっています。今回は輸入する上で気を付ける点や、より安価に仕入れる方法をご紹介します。私は現役で商社の営業をしており、かつ副業として輸入物販を行なっておりますので、自分自身が解決してきた課題についてご参考頂ければ幸いです。
はじめに
本ブログは2部構成です。第2部では各プラットフォームにおける価格比較、及び直接購入をする方法についてご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参考ください。
個人輸入と商業輸入ってどう違うの?

商品を海外から輸入するのは、個人で使用する目的で輸入する個人輸入と、ECサイトや実店舗で販売する目的で輸入する商業輸入の2種類の区分に分かれます。この区分により関税率や手続き方法が異なります。詳しくは税関ホームページに明記がありますのでご確認ください。
主な相違点
| 項目 | 商業輸入 | 個人輸入 |
|---|---|---|
| 目的 | 商業利用 | 自己消費 |
| 対象 | 事業者 | 個人 |
| 手続き | 通関や関税の申告が必要 | 簡易手続きで一定額まで免税 |
| 利用頻度 | 高め | 低め |
個人輸入
- 目的:個人が自分で使うために行う輸入です。
- 対象:自己消費目的の商品を海外から購入します。個人輸入名目で税関へ申告した場合、商業利用は認められません。
- 手続き:少額であれば簡易な手続きで、かつ免税枠が適用されることもあります。ただし一定の金額を超えると関税が課されます。その場合は荷受け時に国内運輸業者へ支払うか、税関もしくは運輸業者から納税書が届きます。
- 課税率:商品の市場価格の60%に基づいた関税率が適用され、課税対象額が1万円以下であれば関税と消費税が免除されることがあります。
商業輸入
- 目的:主に事業者が行うもので、商業目的の輸入です。
- 対象:事業で販売するものが該当します。主に輸入代行業者や卸売業者を仲介します。
- 手続き:輸入手続きや関税申告が必要ですが、仲介業者を介する場合は業者が代行してくれる場合もあります。
- 課税率:商品の市場価格の100%に基づいた関税率が適用されます。
輸入で商品を仕入れる方法ってどんなのがあるの?

商品の仕入れ方法は多岐にわたり、ビジネスの規模や取扱商品によって適切な方法が異なります。以下に、代表的な仕入れ方法とそれぞれの特徴をご紹介します。上級者向けになる程、金額を安く仕入れることができます。
初級者向け

輸入代行業者を利用
海外の商品を輸入する際に、輸入代行業者を利用する方法です。輸入代行業者は仕入元の国によりおすすめの業者が異なります。国際・国内配送や関税手続きを代行してくれるため、輸入経験が少ない方でもスムーズに取引が可能です。
| メリット | 取引がスムーズ。検品・返品代行可能。日本語対応。 |
| デメリット | コストが増える。検品を代行業者で行う場合納期が伸びる。 |

卸売業者(商社)を利用
大型の商品・定期リピート商品・ロット数の多い商品を仕入れる場合、輸入代行業者より安くなる可能性があります。また輸入代行業者は現地のECサイトからの購入しか代行してくれませんが、卸売業者はサプライヤーや現地マーケットからの直接購入も可能です。但し優良な卸売業者は見極めが難しいため、最初のうちは輸入代行業者を利用することをおすすめします。
| メリット | 現地市場からの直接購入が可能。輸入代行業者より保証が充実している。 |
| デメリット | コストが増える。優良な業者の見極めが難しい。 |
中級者向け

現地ECサイトからの直接購入
仲介業者を介さないため、初級者向けより安価に仕入れることが多いです。但し現地の言語で購入・発送追跡・受取確認をする必要があり、かつ不良品があった際の連絡や交渉・返品も自分で行うため、現地言語の日常会話レベルはほぼ必須になります。またECサイトにより、日本人の登録が不可能な場合があります。
| メリット | コストが安い。直接発送のため納期が短い。 |
| デメリット | 言語力が必要。商品の実物確認ができないため不良品が多い。 |
上級者向け

現地からの直接購入
ここからは高レベルの実践経験が必要です。以下その理由をご紹介します。
物販経験:海外市場の相場は非常に不安定です。現地の市場価格とサプライヤーの提示する価格を比較し、日本市場のトレンドを把握したうえで長期的な取引相手になるよう信頼を構築しないと、高額でニーズのない商品を購入するか、そもそも買わせてもらえないことも少なくありません。
言語力:通訳者や交渉代行を仲介すると仕入れ値に影響するため、基本的には現地で起こる全ての課題を自分で解決することになります。最低限、日常会話レベルの言語力は付けましょう。
物販仲間:現地への渡航は当然のことながら長引けば長引く程旅費が嵩むため、基本的には物販仲間と同行し渡航します。短期間でより多くの商材を仕入れ、かつ現地ネットワークを広げ共有するのが狙いです。
販売実績:より市場へ付加価値を提供するには、海外展開に未参入の商品を狙う必要があります。現地のサプライヤーも信頼・実績もない外国人と商売はしたくないため、交渉できる材料はあらかじめ用意する必要があります。
このレベルになると商社や卸売業者が行なっている仕事とほぼ同じ内容になるため、仕入れること自体を仕事にできます。以下、実際に依頼される内容をご紹介します。
上級者ができること
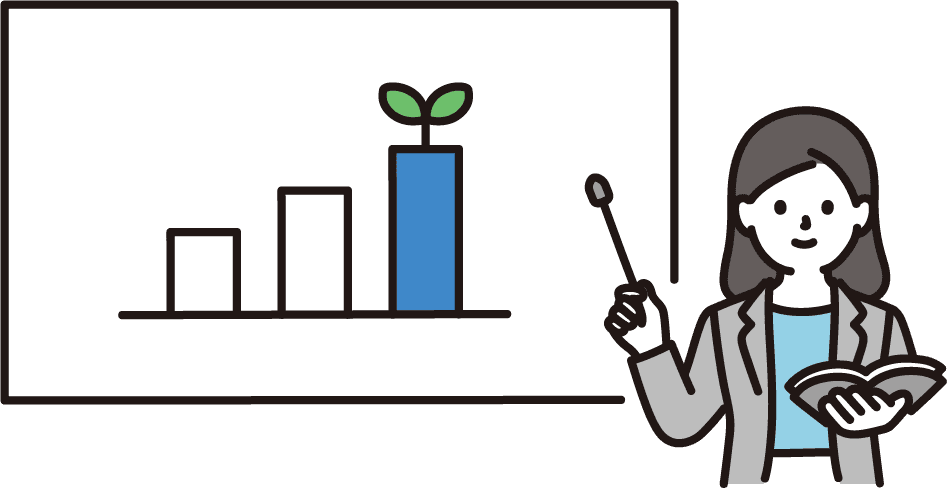
現地サプライヤーとの直接交渉
現地のメーカーと直接仕入れ交渉ができます。交渉にはある程度会社の知名度や販売実績が必要になりますが、日本への進出を視野に入れており未参入の商材は、独自販売権を獲得すればシェアを独占できるため個人規模とは比較にならない程の商売が可能です。
独自販売権とは?
特定の商品やサービスを、指定された市場や地域で唯一販売できる権利を指します。この権利を得た販売業者は、その権利だけで差別化を図れるため、高い利益率や市場シェアを獲得できます。但しその反面、最低注文数や販売目標などの契約を条件とする場合があります。
主な特徴
- 独占的権利: 指定された市場で同じ商品を販売する競合他社を排除できます。
- 契約期間:一定の契約期間に基づいて与えられます。
- 権利取得条件:最低注文数や販売目標などの条件が含まれます。
見本市・展示会からの仕入れ
見本市や展示会で最新の商品情報を確認し、サプライヤーと交渉して仕入れ契約をします。また出店業者は販売代理店を探している場合も多く、OEM商品開発も携わることができます。
OEM商品開発とは?
自社ブランドを立上げ、販売を行うためメーカーに商品を委託生産することを指します。自社の仕様に合わせて商品を製造してもらえ、独自ブランドの展開が可能になります。
- メリット:独自ブランドとしての販売が可能。製品に関する仕様変更も自由度が高い。
- デメリット:初期費用が高い。製造ロットが大きく在庫リスクも高くなる。
どこの国から仕入れるのが良いの?
 新野くん
新野くん物販を始めたいからおすすめの国を教えて!
 くろひつじ
くろひつじメーン!まずは外国語のスキルがあるなら、その国にした方が他の人との差別化ができるね!スキルがなくても仕入れる商品のジャンルを決めればある程度国も絞れるよ。
ブランド品
まず前提として、ブランド品の価格は国によってそれ程の相違はありません。もしブランドが国毎に価格を決め、一部の国で低価格で販売すれば自社のブランド価値が落ちてしまうからです。
一部の新興ブランドは期間限定で価格を落とす場合もありますが、あくまで一定期間のため長期的な商材にはなりえません。また海外にはブランドのコピー品が数多くあるため、ブランド品の物販を行う場合は国内の実店舗から仕入れを行う店舗せどりをおすすめします。
店舗せどりについては以下のサイトで解説しています。
その前提の基、どうしても輸入でブランド品を取扱う場合は、その原産国から購入する方法が最も安価です。理由は、現地の横流し品があるためです。ブランド品の原産国・市へ渡航したことがある方なら見たことがあるかもしれませんが、正規店と比べ圧倒的に安く、素材やブランドロゴが正規品同様の商品が売っていたりします。
正規代理店ではないため販売証明書やロットNo.は発行してくれませんが、素材やロゴなどは同じため並行輸入品として販売できる可能性があります。但しブランド品は飛行機へ持込む際、模範品は没収され市場価格20万円以上の商品は課税というルールもあります。基本的に輸入はおすすめしません。
玩具・アパレル用品・日用雑貨
中国からの仕入れをおすすめします。昨今、玩具やアパレル用品、日用雑貨の原産国は東南アジアが多いですが、東南アジアはまだ有効な仕入れプラットフォームはありません。東アジアと比較し商品の品質も悪いため、品質・価格・及び供給ルートも安定している中国から仕入れるのが一般的です。中国ブローカーの仲介手数料も発生はしますが、販売価格に影響するほどではありません。
コスメ用品
韓国ブランドが圧倒的に人気が高いため、韓国仕入れ一択になるかと思います。韓国は渡航費用もある程度抑えられ、かつ言語的な難易度も低く、ECサイトも充実しています。コスメ用品は物販の参入難易度が低いため、初心者は韓国輸入からトライすることをおすすめします。
物販の参入難易度とは?
中国から仕入れるには?
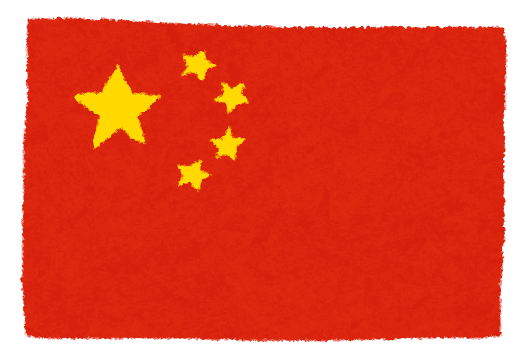
中国仕入れは他国と比較し商材のジャンルが豊富にあるため、事業の拡張性があり最もおすすめできます。今回は私が実際に使っている輸入代行業者をご紹介します。全て月額会費は無料で、日本語に対応。輸入品の検品も代行できます。
1.ラクマート

代行手数料:商品代金の3~5%
中国輸入代行業者の代表格です。輸入頻度や数により代行手数料が安くなり、仕入れロットが多い場合は月額プランにも変更が可能です。オプションにタグ付けや梱包もしてくれ、チャットで連絡対応してくれます。
但し輸入規制品に慎重で、ブランド類似品や口につけるもの(水筒)など、輸入を断られる比率が最も高い代行業者でもあります。市場調査に時間を掛けたのに輸入できないことが頻繁にあるため、まず見積もり依頼からすることをおすすめします。
2.Chinamart

代行手数料:商品代金の5~11%
こちらの代行業者も利用しています。代行手数料が高いため、利用用途としては下記になります。
- 規制品に対して比較的融通がきくため、ラクマートで断られた商品を仕入れる。
- 一括直送プランを利用する。(手数料1%で事前検品なし)
3.転送ネコ

こちらを利用するメリットは、淘宝購入の支払代行が利用でき、代行業者への倉庫納入や事前検品の過程を省くことができます。但しクレジットカード払いに対応していないため、毎度銀行振込みを行う必要があります。
輸入代行業者の事前検品って実際どうなの?

私は事前検品を利用していません。その理由を補足としてご紹介します。あくまで個人の意見ですのでご参考程度にお考え頂ければと思います。
輸入代行業者が見落とした不良があった場合、その旨の連絡をすると輸入代行業者経由で中国の販売業者へ確認してもらえます。但し、それでも解決しなかった場合は荷受け日から平均10日~15日以内に返品・返金をする判断をしないと泣き寝入りになります。購入点数が大きくなれば自社で行う検品作業はそれ相応の時間を要すため、日数が限られるのはデメリットになります。
事前検品を頼むと輸入代行業者の倉庫で検品してくれますが、多くのユーザーの商品を限られた倉庫スペースに保管する必要があるため、その環境はあまり良くない可能性があります。最初の内は販売元側の梱包状態によるものの可能性があり諦めていましたが、直接購入をしてからは商品状態を比較でき、私は利用しない判断をしました。
まとめ
今回は中国仕入れに関する概要をご紹介しました。物販は参入障壁が低く再現性が最も高い分野のため、自分の看板で商売を開始するにはまず最初に取り組んで頂きたい分野の1つです。以下ブログでは各プラットフォームにおける価格比較、及び直接購入をする方法についてご紹介しておりますので、ぜひ合わせてご参考ください。





