私は現役で商社の営業マンをしています。一部の業界に限った話ではありませんが、特に商社の営業は一日の所定労働時間内では終えられない程の業務量を抱えることが一般的です。
しかしそんな中でも、トップに近い営業成績を残しながら必ず定時に終わって家に帰る人がいます。彼らはどのような仕事の進め方をしているのでしょうか。また他の人との違いはなんでしょうか。
今回は私の周りにいる生産性がバグっている人たちの話を基に、その特徴を業務スピード・効率化の観点からご紹介します。

- 日々業務量の多さに疲弊しているビジネスマン
- 社内業務の振り分けに困っている経営者
業務スピード
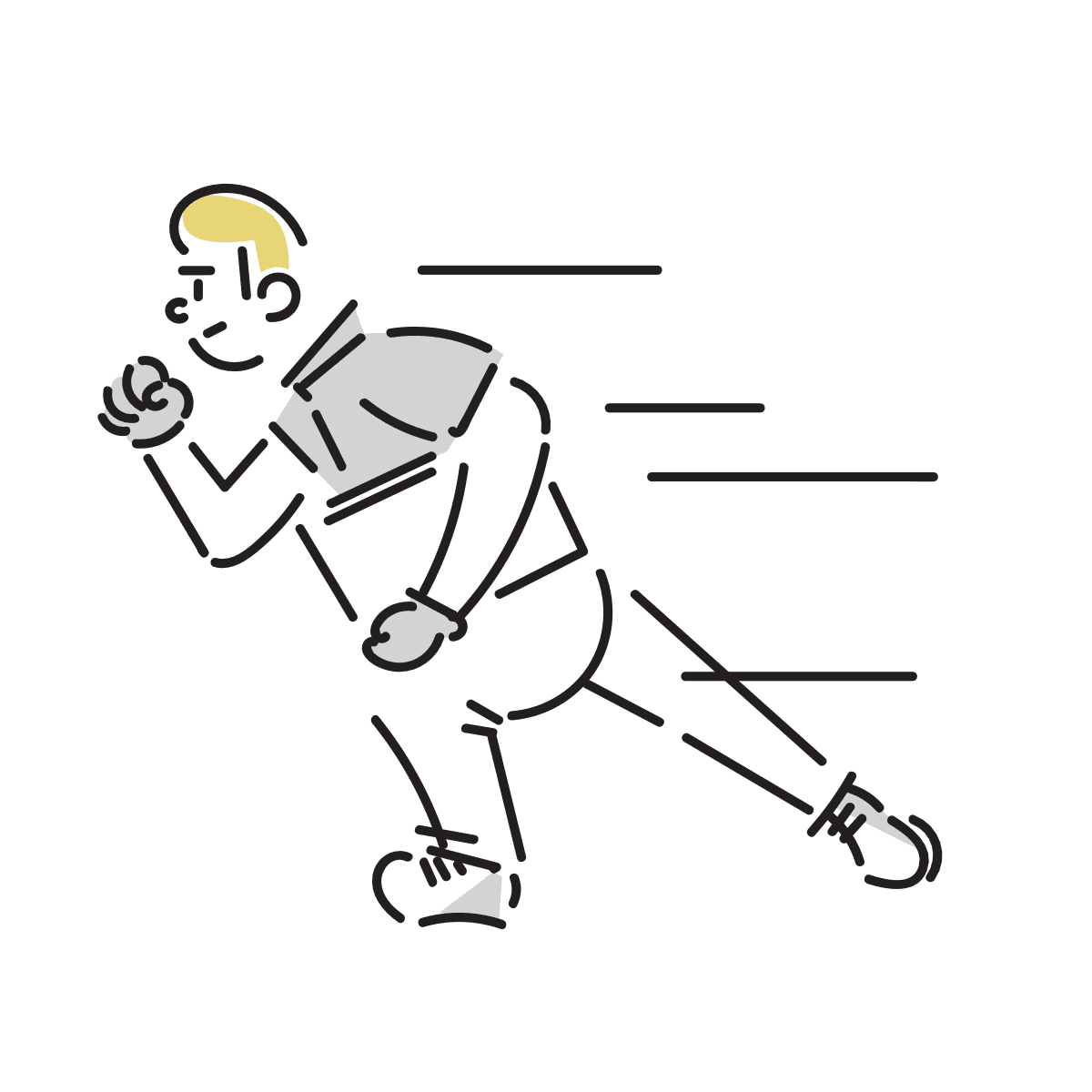
 新野くん
新野くん業務量が多くても定時で帰る人は仕事のスピードが早いよね。



メン!そうだね。じゃあ仕事のスピードを早める要因はなんだと思う?



それは個人の特性によるものじゃないかなあ。簡単に真似できるものじゃないと思うけど…。



確かに個人の特性はあるけど、それだけでは正確性が無くなってしまうんだ。正確に・かつスピードが早い人は、再現性がある特徴があるんだメン!
業務スピードは個々の特性で異なる。と思われるかもしれませんが、これは間違っている側面があります。圧倒的な業務量をこなす人は、以下のような再現性のある特徴があります。
残業をしない
業務スピードが早いから残業をしないのではなく、残業をしないから業務スピードが早いのです。
日本において、多くの会社は残業をすることが評価対象となってきました。それが長い間、日本の生産性が落ち続けている要因の一つだと言われています。
残業には業務終了時間を予め決めることができないという特徴があります。仕事が終わったら終了する、という不確実性のあるルールを自分に定めると、人間は所定労働時間内も余力を残そうとします。
労働時間と生産性の関係
厚生労働省の報告によると、労働者1人当たりの年間総労働時間が長くなるほど、労働生産性は低下する傾向があるとされています。具体的には、年間総労働時間が1,215時間のときに労働生産性が最大となります。
これは労働日数が20日/月の計算で1日当たり5時間程度の労働時間です。
残業と生産性の関係
Slackの調査によると、残業をする人は定時に切り上げる人に比べて優先順位が競合することで生産性が妨げられていると感じる割合が50%高いとされています。
優先順位が明確
優先順位は業務スピードに直結します。重要な仕事は朝の頭が働いている時間帯に終わらせ、その他の業務を順位毎に終わらせていきます。
これを可能にするのは、前述した業務終了時間を明確にすることが重要です。優先順位とは、始まりと終わりの時間が明確になって初めて効力を発揮します。
判断が早い
優秀な人は判断が早い。と見られがちですが、実際には優先順位の低いことの判断が早いだけです。ファーストリテイリングが掲げる即断・即決・即実行にもあるように、判断のスピードは生産性を大きく左右します。
フロリダ州立大学の社会心理学者であるロイ・バウマイスター教授は、人間が1日に判断できる回数には限界があると述べています。判断が積み重なることで判断疲れが生じ、重要な場面での判断ミスや衝動的な行動が増えます。
よって、再現性のある判断を早める方法は以下の通りです。
- 物事すべてに優先順位を決め、重要でない内容に判断エネルギーを使わず即決する。
例えばFacebookの創設者であるマーク・ザッカーバーグ氏や、Appleの共同創設者であるスティーブ・ジョブズ氏などは、毎日同じ服を着たり判断する時間制限を決め、より重要な意思決定にエネルギーを集中させています。
注意点として、5分以内に判断した結果は熟考した結果と変わらない。と言う人がいますが、これは脳科学上証明されているものではありません。重要なことは熟考しましょう。
参考文献:STUDY HACKER
自己肯定感が高い
自己肯定感が高くすることは、自身が判断した結果を受け入れ軌道修正をする、軌道修正のスピードを上げる効果があります。もし自身の判断により失敗した場合でも、自己肯定感が高い人は後悔より先に軌道修正に舵を切ります。
具体的に自己肯定感が高まる取り組みは以下の通りです。
本業や副業の中で成功体験を積み重ねる
本業で新規の案件を獲得したり、自身がオーナーとなる副業で1円でも稼いだら、それが成功体験となり自己肯定感が高まります。これは非常に重要で、継続に繋がる最も大きな要因にもなります。
逆に一定期間成果の出ない取り組みは、事業転換や転職などで軌道修正することをおすすめします。どの業界にも顧客とのニーズが合わないことは必ずあります。
定期的な有酸素運動をする
仕事はどんな業界・役職でも体力勝負です。以下の通り、定期的な運動は仕事のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
集中力と認知機能の向上
運動は脳の血流を増加させ、認知機能や集中力を高める効果があります。これにより、タスクへの集中度が向上し、業務の効率化が期待できます。
ストレスの軽減
定期的な運動はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、精神的なリフレッシュ効果をもたらします。これによりストレス耐性が高まり、仕事中のプレッシャーに対処しやすくなります。
エネルギーレベルの向上
運動習慣を持つ人は、持久力やエネルギーレベルが向上し、疲労感を感じにくくなります。これにより、長時間の業務でも高いパフォーマンスを維持できます。
メンタルヘルスの改善
運動はうつ症状や不安感の軽減にも効果があり、精神的な健康状態の改善を通じて、仕事への意欲やモチベーションの向上につながります。
参考文献:ライフハッカー
行動の効率化
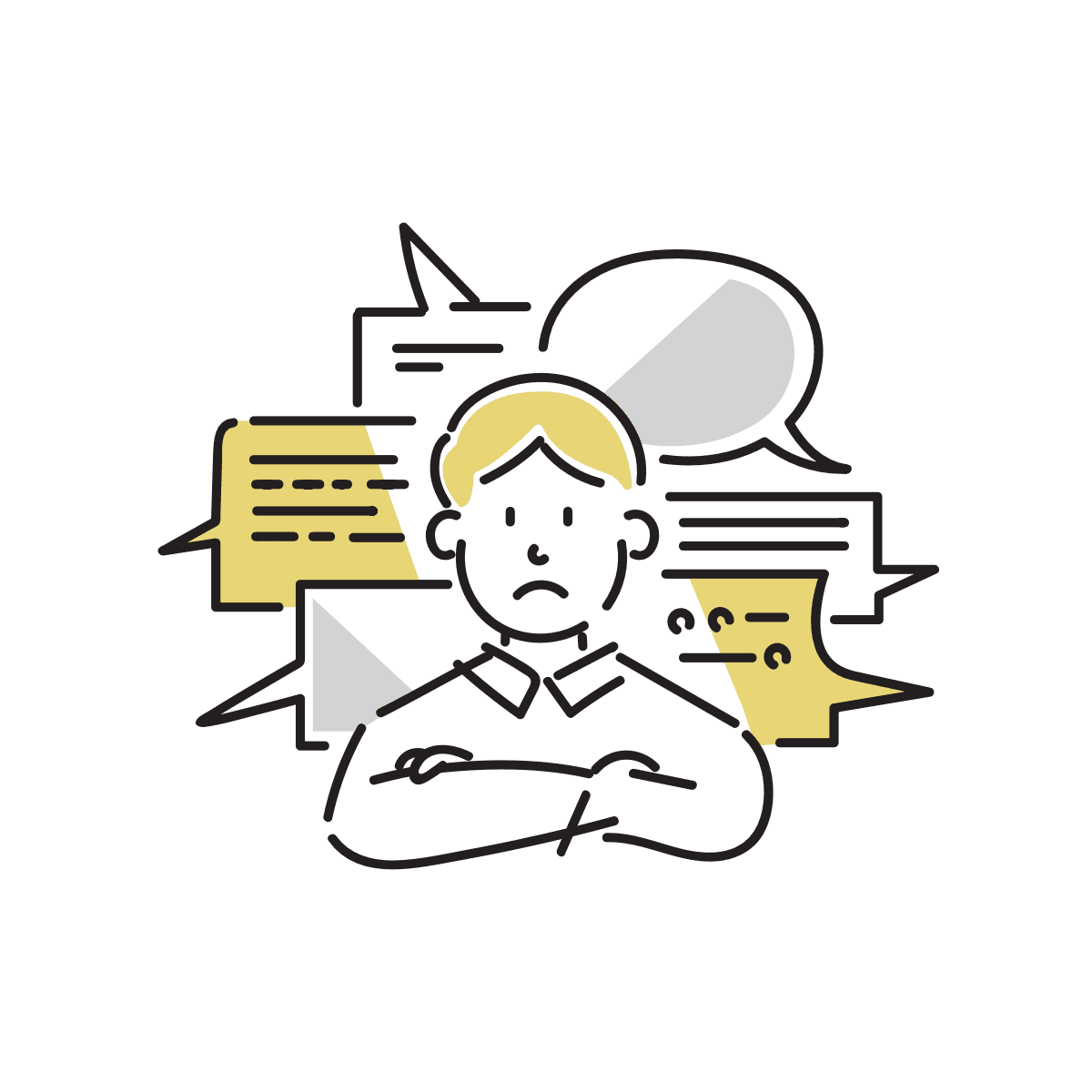
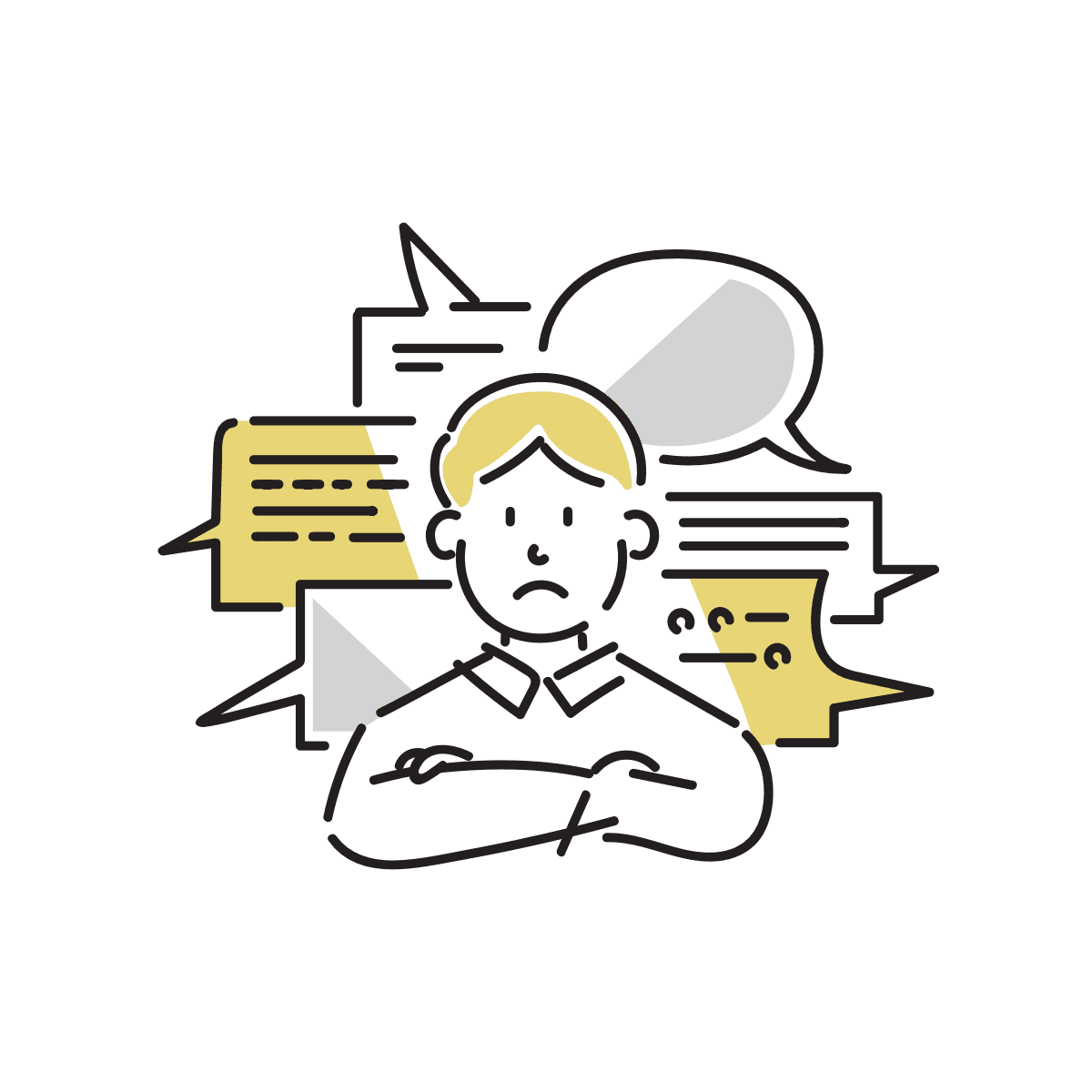
次に、行動を効率的にする方法をご紹介します。業務内容は千差万別であり、かつ会社から雇われている従業員の場合、業務プロセスを自分だけ変えるのは現実的ではありません。
その反面、行動はどんな業界でも一定の共通性があり、自分だけ違った場合でも特に問題にはなりません。
人間関係の取捨選択を行う
仕事において人間関係は非常に大切です。営業に関しては、特に取引先とは良好な関係を築き長期的なWin-Winを計るべきです。しかし会社の愚痴ばかりを言う同僚・先輩や、労力と報酬が見合わない取引先には時間を割いてはいけません。
時間は有限です。以下の2点を知り、意識することが重要です。
Win-Winではない取引先を排除する
ビジネス思想家のスティーブン・R・コヴィー氏の著書7つの習慣によれば、自分と相手どちらも勝者になれなければ、結局はどちらも負けなのである。と語っています。
取引先と長期的な関係を築くことは大切ですが、それはWin-Winの関係性である前提の上に成り立っています。自社、もしくは取引先が譲歩する取引は積極的に排除すべきです。
共感できない人とは距離をとる
アメリカの起業家であるジム・ローンは、人は周りにいる5人の平均値でできていると語っています。
また英科学誌『Nature』に掲載された論文では、貧しい家庭の子どもが裕福な友人を多く持つ環境で育つと、成人後の所得が約20%増加することが報告されています。
限られた時間は、同じ考えを持つ人・もしくは相手の話に共感できる人と共有しましょう。例えお金の面ではWin-Winであっても、共感できない取引先・会社の人といるのは辛いものです。
パレートの法則を意識する
経済学者ヴィルフレド・パレートは全体の成果の約80%は、20%の原因によって生み出されると提唱しています。パレートの法則、もしくは8対2の法則とも呼ばれます。
しかし厳密に言えばこれは結果論です。自身の取り組みの中でどれが成果に繋がるか、事前に予測することはできません。重要なのは意識することということを覚えておきましょう。
具体的には、以下の内容を意識することで不要な時間を排除できます。
重要な顧客を特定
- 成約実績から算出した売上の2割を占める主要顧客を特定し、関係構築の時間を集中する。
仕事の再現性
- 成約実績から算出した売上:8割・タスク:2割の案件を特定し、再現性を検証する。
適用される分野
パレートの法則は、以下のような多くの分野で適用可能です。
| 分野 | 結果8割・要因2割の法則 |
|---|---|
| ビジネス・経営 | 売上の80%は、20%の顧客が生み出す。 |
| プロジェクト管理 | 80%の進捗は、20%のタスクが生み出す。 |
| マーケティング | 80%の利益は、20%の商品が生み出す。 |
| ソフトウェア開発 | 80%の不具合は、20%のバグが原因。 |
| 時間管理 | 80%の成果は、20%の活動から生じる。 |
| 人間関係 | 80%の満足感は、20%の人間関係から生じる。 |
最後に
今回はスピードと効率の観点から、再現性のある法則や特徴についてご紹介しました。
日本のビジネスマンは実直に働く国民性から、会社から無限にタスクを要求されることが多いと思います。このブログの内容を参考にして頂き、余裕を持った時間配分を意識して頂ければ幸いです。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。





