私は現役で商社の営業マンをしています。営業や営業事務に就職して一番最初にやることは、PR活動から検収までの一連の流れを覚えることです。
この流れは例外なく物件ごとに行われますが、就職したばかりの人や経験が浅い人の中には、この認識が曖昧な人がいます。
そこで今回は、営業や営業事務が対応する過程の全容から、実践で活かせる知識をご紹介します。

- 営業、もしくは営業事務に就職したばかりの人
- オペレーションを他社と比較したい人
 新野くん
新野くん営業ってマニュアルが無い会社が多いから、疑問点を解決するには上司ガチャに当たるか自分で調べるしか無いんだよね。
 くろひつじ
くろひつじメン!そうだね。一昔前は上司に「社内営業力が鍛えられるから他の人に聞け」なんて言われた時代があったくらいだからね。
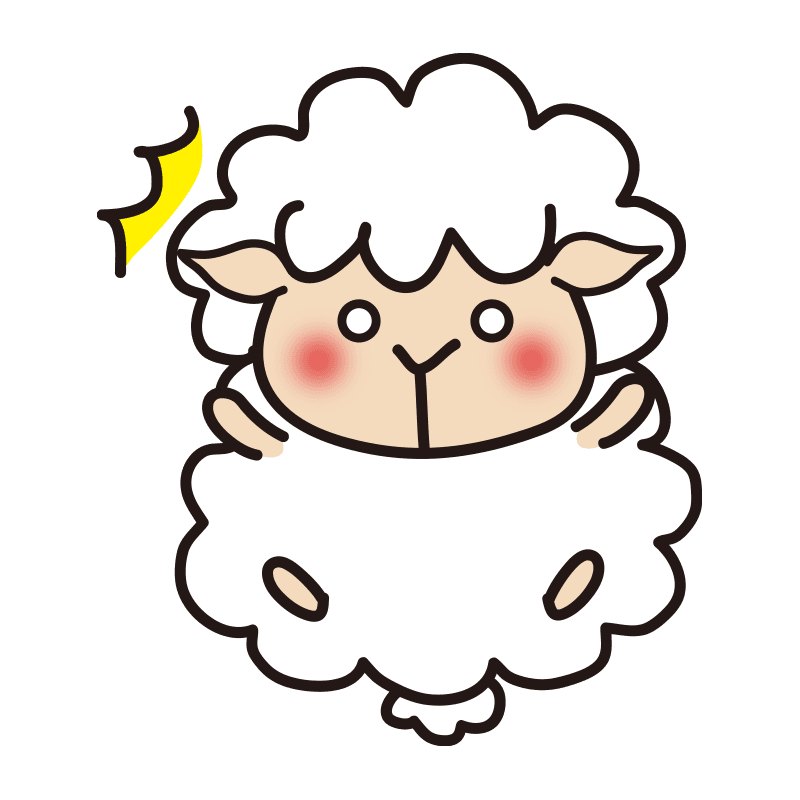
- この記事を読み終えた皆さんは、令和の商人である。
営業とは

営業とは、新規顧客の開拓から既存顧客の対応、アフターサービスまでを包括的に行う人のことを指します。
その役割の多様性から他の職種より業務量が多く、給与にはみなし残業制度が導入されている場合もあります。

みなし残業制度(固定残業代制)とは、会社が従業員に支払う給与に、あらかじめ一定時間分の残業代を含める制度です。営業職は外回りや直行直帰が多く、残業時間の把握が難しいため、この制度が適用されることがあります。
厚生労働省の令和4年就労条件総合調査によれば、みなし残業制度を採用している会社の割合は14.1%と報告されています。
これは全職種・全業種を対象とした割合であり、営業に対象を絞ればその割合は30%を超えると考えられます。
営業の現実
他の会社や職種の人から見ると、営業は成果主義のような側面があると考えられていますが、実際にはB2B取引を行う会社のほとんどが年功序列を採用しています。
その理由は、B2Bの企業間取引を主とする会社は既に顧客と定期的な取引を行なっていることが一般的で、ルート営業の成果は、会社の看板があってこそと判断されるためです。
逆に言うと、B2Cを主とする会社で新規開拓の営業であれば、属人的な成果と判断される可能性があります。
しかし、このような会社は基本給が低いことが多く、かつ営業職を個人事業主として外部委託し、完全歩合制を採用している場合もあるため、一般的に給与の安定性はありません。

ルート営業とは、既存顧客を相手にする営業を指します。顧客と営業の会社は既に関係性を持っており、新規開拓と比較して難易度が低い特徴があります。ルート営業は「育てる営業」と言われ、顧客との長期的な関係性が重視されます。
STEP1 PR活動
さて、ここからは具体的な流れに沿ってご紹介します。
PR活動とは、営業職の間で使われる用語で、自社の商品やサービスを顧客に紹介する活動のことを指します。顧客から見積もり依頼がくる前には、その顧客が「この商品が欲しい」と思う過程が存在します。
この顧客が商品を認知することを意図的に行う活動をマーケティングと呼びます。営業のPR活動とは、このマーケティング手法の1つとして分類されます。
 くろひつじ
くろひつじマーケティングはすごく広域的な概念なんだ。マーケティングにおける4PのPromotion(販促)が営業活動に分類されてるね。
マーケティングについては以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

営業がPR活動をする過程には、以下のようなパターンが存在します。
顧客からこの商品が欲しいと要望があった場合
B2B取引における顧客の要望は、要求仕様書として送付されます。例えば営業が商社である場合、自社と商流のある会社の中から要求仕様書に沿った商品を取り扱うメーカーを探し、メーカーと共にPR活動します。
また営業がメーカーである場合には、自社で対象の商品を取り扱っているか確認します。確認する方法は社内の製造部署に聞いたり、過去の販売実績を参照します。
商流については以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

社内又はメーカーから自社の商品を販売したいと要望があった場合
逆に、社内もしくは商流のあるメーカーから拡販希望がある場合もあります。この場合には顧客へPRしたい商品の概要を伝えたうえで、了承が得られればPR活動を行う日程をアポ取りします。

要求仕様書とは、顧客が「どういう機能が必要か」「お金を支払う条件」などをまとめた文書を指します。B2B取引では物件ごとの金額が高く、要求仕様や検収条件を書面に残すことで、仕様を満たしていない場合には支払い義務を生じない念書を得ることができます。
STEP2 見積もり
上述したPR活動がうまくいけば、顧客から正式に見積もり依頼の連絡がきます。
メーカーの場合
自社がメーカーである場合、社内の製造や開発に対象の商品を制作する工数を確認。また社内の購買には、購入品の金額を確認します。
発生する工数には人件費チャージを乗せ、また購入品には粗利益を上乗せし、顧客に見積もりを提出します。
商社の場合
自社が商社である場合、その商品を取り扱うメーカーへ見積もりを依頼します。メーカーから見積もりを受け取ったら、その金額から何%かの粗利益を上乗せし、顧客へ見積もりを提出します。
見積もりに粗利益を乗せる方法は以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。


人件費チャージとは、時間もしくは日当たりの人件費を指します。メーカーは日数や人数を見積もりに記載しない場合もありますが、必ず見積段階で計算しています。
STEP3 注文(手配)
依頼した商社やメーカーから見積もりを受け取ったら、顧客は社内の購買部署へ注文書の発行を依頼(手配申請)します。購買はその見積もり金額が適正かどうかを判断したうえで、以下の手順を行います。
相見積の場合
複数の会社へ同じ要求仕様の見積もりを依頼し、その価格差で依頼先を決めます。依頼先が仕様を満たさなければ、競合先とは認められません。
異なる商社が同じメーカーで相見積をする場合もあれば、異なる商社が異なるメーカーで相見積する場合もあります。但し、前者はメーカー側が複数の商社へ見積もりを提出することを了承する場合に限定されます。
一社選定の場合
複数の会社へ見積もりは依頼せず、最終見積の提出を選定先の商社やメーカーへ依頼します。競合がいない一社選定は以下の条件に該当する必要があります。
- 既に導入済みの商品・サービスと同等のものを依頼する場合。
- 既に導入済みの商品・サービスの修理、改善、改造、かつ他社では実施不可の場合。
- 上記いずれかに該当し、かつメーカーが導入時に仲介した商社にしか見積もりを出さない場合。
つまり、他のメーカーでは要求仕様を満たせない場合、かつメーカーが導入時の商社にしか見積もりを出さない場合は一社選定となります。
相見積に勝つ方法は以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

STEP4 制作~納品
商社やメーカーは顧客から注文書を受け取ったら、社内でエントリー(受注処理)を行います。エントリー後は、以下の工程を上から順に行なっていきます。
メーカーの場合
| 工程 | やること |
| 納期確認 | 全体スケジュールを作成し、納期を顧客と共有します。 |
| 設計・開発 | 商品構想を書面化し、その内容を顧客と共有します。 |
| 購入品手配 | その商品に必要な部品で自社が制作できないものがあれば、他社から購入します。 |
| 外部委託 | その商品に必要な作業で自社が対応できないものがあれば、他社へ外注します。 |
| 中間報告 | 制作を終えた段階で、顧客と動作テストを行い仕様を満たしているか確認します。 |
| 納品 | 商品を納品します。 |
| 提出物 | 設計・開発で書面化した最終版を提出、必要であれば取説も作成します。 |
商社の場合
| 工程 | やること |
| 納期フォロー | 全体スケジュールを管理し、問題が発生した際には納期の再設定を行います。 |
| 設計・開発 | 顧客とメーカーで構想を共有する打ち合わせにて議事録を作成します。 |
| 支給品手配 | その商品に必要な部品でメーカーが制作・購入できないものがあれば、自社で購入します。 |
| 中間フォロー | 顧客との中間報告前に商品を確認し、不具合があれば修正を依頼します。 |
| 中間報告 | 顧客とメーカーによる動作テストにて議事録を作成します。 |
| 調整フォロー | 顧客への納品前に商品を確認し、不具合があれば修正を依頼します。 |
| 納品 | メーカーから受け取った商品を確認・納品します。 |
| 提出物 | メーカーから受け取った提出物を確認・提出します。 |
議事録の作成方法は以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。
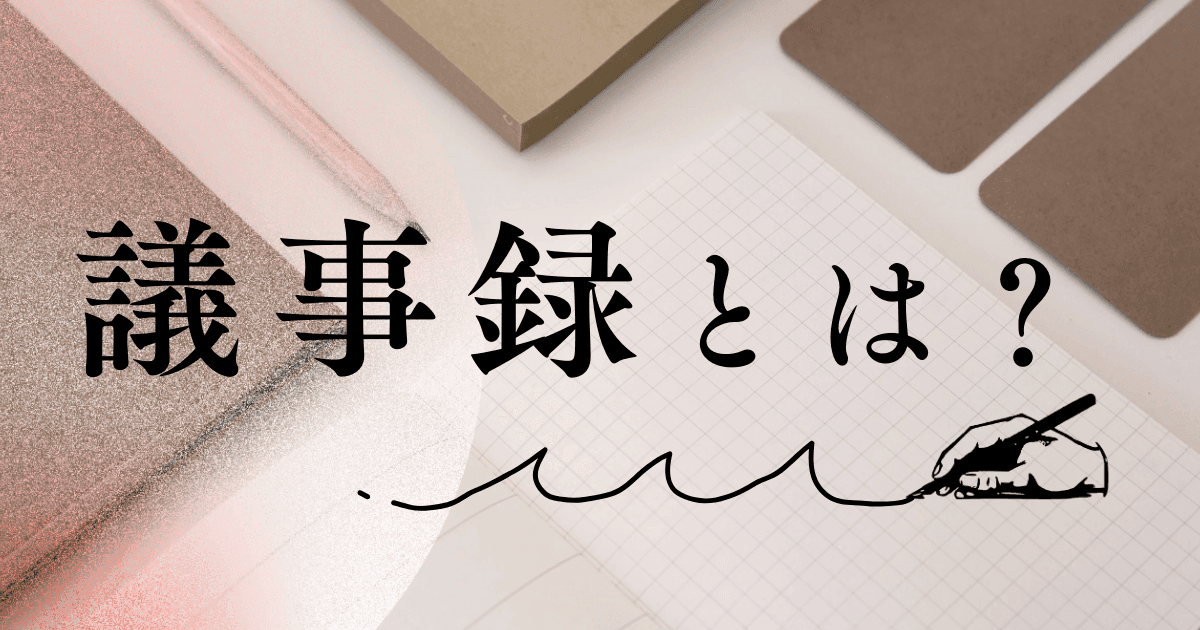
補足
上記はすべての業界に共通する項目だけをあらわした表となります。
例えば産業設備を納入する場合は工事が絡むため、以下のようなタスクが発生し、商社は下請の数だけそれぞれの会社に発注する必要があります。
| 作業 | 対応者 | 会社 |
| 顧客の要望をヒヤリングする | 営業 | 商社 |
| 設備を設計する | 設計 | メーカー |
| 購入品を手配する | 購買 | メーカー |
| 支給品を手配する | 営業 | 商社 |
| 支給品を運搬する | 運搬業者 | 下請 |
| 設備を製作する | 製造 | メーカー |
| 設備を調整する | 品質 | メーカー |
| 設備をバラす | 製造 | メーカー |
| 設備を運搬する | 運搬業者 | 下請 |
| 設備を横引きする | 重機業者 | 下請 |
| 導入箇所の清掃をする | 清掃業者 | 下請 |
| 導入箇所のケガキをする | ケガキ業者 | 下請 |
| 導入箇所へエア配管や電気配管を延長する | 配管業者 | 下請 |
| 導入箇所へエア配線や電気配線を延長する | 配線業者 | 下請 |
| 導入箇所へ通信ケーブルを延長する | 通信業者 | 下請 |
| 設備を復旧する | 製造 | メーカー |
| 設備を精度調整する | 品質 | メーカー |
 くろひつじ
くろひつじめちゃくちゃいっぱいあるよね…。これが商社が多忙だと言われる所以なんだ。
STEP5 検収
検収とは一般に納品物を受け取ることを指しますが、営業の間では支払いの意味も持ちます。顧客への納品を終えたら、要求仕様や検収条件を満たしているか、顧客との打ち合わせにて最終チェックを行います。
そこで検収条件を満たしている場合には無事検収されますが、もし満たしていない場合には満たすまで検収されません。
不具合が発生する可能性
例えば提出物が足りない場合や、商品の簡単な修正であれば、その月内に検収されることが可能です。しかし、深刻なバグや不具合が発生した場合には、修正まで数ヶ月の納期がかかる可能性があります。
例えばその不具合が顧客の要求仕様通りに制作した結果発生し、かつ動作テストでは発生しなかった(顧客の環境下でしか発生しない)場合を考えてみましょう。
制作は要求仕様通りにしており、事前動作テストも問題ないため、下請法に則るとメーカーへの支払い義務が生じます。しかし顧客側からすれば、不具合のある商品を検収することはできません。

下請法(正式名:下請代金支払遅延等防止法)とは、不当な値引きや返品の強要、支払い遅延などを防止する法律です。下請が発注会社より資本金が少ない場合に適用されます。
検収月がズレる可能性
下請法は2024年の改正により厳格化されましたが、それ以前までは不具合の修正完了まで、支払いを待ってもらうことは珍しくありませんでした。
しかし現在では、明らかなメーカー責任による不具合でない限り、支払いの遅延は認められません。
ここで商社が仲介していれば、メーカーへ先に支払いを終え、バグ修正の追加費用を注文します。商社が仲介していない場合には、顧客とメーカーで落とし所を探ります。
このような不具合のトラブルや検収月のズレは、一見するとイレギュラー対応のように思えますが、実はほぼ毎日このような問題が発生しています。
その度に営業が対処するため、これがストレス耐性があり人間関係が得意な人が向いていると言われる所以です。
最後に
今回は、営業や営業事務が対応する過程の全容から、実践で活かせる知識をご紹介しました。
営業や商売のスキルは特定の資格がなく言語化が難しいため、長く勤めると自分にスキルが身に付いているか、不安になることも多いと思います。
しかし、いろんな会社の商売に最前線で触れている、もしくは触れることになる皆さんは、間違いなく商売のプロです。自信を持って、令和の商人として日々の営業活動を行いましょう。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。



