私は現役で商社の営業マンをしています。商社に関わらず、日本における多くの会社は変化を嫌う傾向にあります。一方で、若い世代や中堅層では、会社組織は変化し続ける必要があると考える人も少なくありません。
この要因は世代間による考え方の違いや、それぞれの役職における役割の違いによるものです。会社によってその違いの大小はありながらも、どこの会社でも少なからず起きている事象といえます。
今回は変化を嫌う会社をテーマとし、その改善方法や会社員が取るべき対策についてご紹介します。

- 変化を嫌う会社に対して不満に思っているビジネスマン
- 自社の新陳代謝の低さを懸念している経営者や管理職
 新野くん
新野くんうちの会社も全然変化しようとしないんだよね。今後市場が縮小していく業界だから、将来が不安なんだけど、、
 くろひつじ
くろひつじメン!それは少なからずどこの会社も似たような特徴があるんだ。今回は会社員の視点に立って、その対策を紹介するよ。
若い世代や中堅層を中心に、自社に対して不満に思っている人は少なくありません。その不満自体は大概正しいものですが、その改善方法は間違っている人が多いように思います。
年齢や性別、家庭環境に関わらず、役員や経営者以外の人にとって会社はただの止まり木です。そしてその止まり木は、どんなに優秀な鳥が手入れしても寿命を終えれば必ずなくなります。
例えば変化しない会社に対して不満に思っている場合、まず自分自身が変化していく必要がある前提は認識しましょう。その行動は会社に決定権がなく、逆もまた然りです。
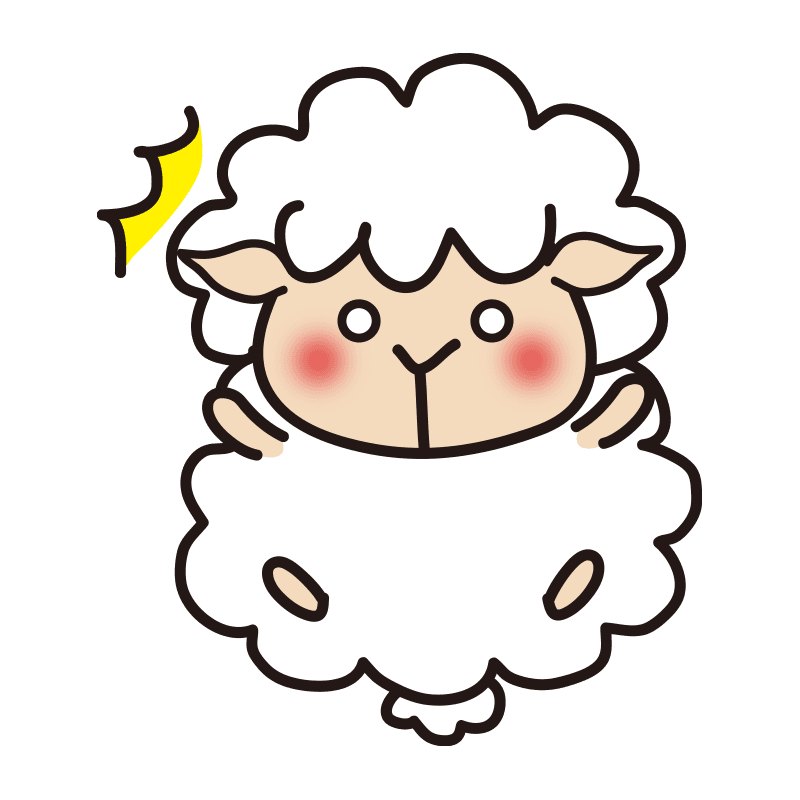
- 会社員にとっての顧客とは、取引先ではなく所属している会社である。
- その会社が変わろうとしないのは、有権者が自身の役割のみ直視しているからである。
- 会社が変わる唯一の方法が業績の悪化であり、会社員は自分の将来性を自分で築く必要がある。
前提情報
日本における終身雇用や年功序列は、時代とともに無くなりつつあります。例えばアメリカは戦後の高度経済成長期において、日本同様の年功序列や終身雇用といった雇用形態を採用していました。
しかし1970年代から1980年代にかけて、日本企業の台頭により製造業が大きな打撃を受けたことを背景に年功序列・終身雇用制度は徐々に崩壊し、多くの企業が成果主義的な人事制度を導入していきました。

雇用形態が切り替わった1980年以降、アメリカの経済成長率は目に見えて成長しています。当然ながら経済成長率の差は他にも要因がありますが、現在に至るまで日本との差は広がり続けています。
日本においてもコロナ禍以降、経済成長率は徐々に上がり初めていますが、物価高や円安の影響による側面が非常に高く、実際に購買力に繋がる実質賃金は下がり続けています。
ある意味で自国を犠牲にしたこの政策は、表面的なGDPだけを高く見せるものであり、政府はこの区間で終身雇用や年功序列の廃止を模索しています。
参考文献:東洋経済
会社員の顧客は所属している会社である
終身雇用や年功序列が無くなりつつある現代では、皆さんは自分派遣会社の社長と言えます。会社員の顧客は所属している会社であり、その会社の取引先は自分の顧客ではありません。
会社が変化を拒むのであれば、それは皆さんの顧客が継続を拒んでいるのと同義です。反面教師として転職に活かしたり、副業を始める良い機会として捉え、今後その会社と継続的な取引をするか冷静に見極めましょう。
ただ不満を持つのではなく、自分という人材を高く買ってくれる会社を手伝い、沈む船は早々に降りても何ら問題はありません。
変化に対して柔軟な会社の比率
但し、転職において次の会社が目的通りになる確率は決して高くはありません。
単独経営のいわゆるオーナー社長は、サラリーマン社長と比べ当事者意識が高い傾向にあります。もちろん本人の性格や経歴にもよりますが、当事者意識が高ければ変化に対して柔軟な対応をする比率も高くなります。
しかし、日本における単独経営の会社は全体の10%に限られており、かつソフトバンクグループ等の大手企業では相対的に倍率も高くなります。
会社が変化しない要因

同じような特徴を持つ会社に転職するリスクを回避するには、その要因について自分が認識する必要があります。本章では、会社が変化を拒むその理由についてご紹介します。
それぞれの役割
会社組織では、それぞれの役職毎に役割が明確に分かれています。会社組織における役職は下図の3種類に分類でき、それぞれが個々の役割を循環させて初めて組織として機能します。

例えば就職氷河期の時代では、下から上へ循環する概念を持たない会社が多くありました。このような時代を生きた当時の社員は、同様の概念を現代まで持ち続けている人も少なくありません。
特に日本におけるサラリーマン社長や管理職は半ば株主のような側面があり、現場の実績や社員の実績に関与せず、ただ会社の実績だけを直視している人が大半を占めるのが実情です。
会社の実情
変化に対して決定権を持つ経営者がこのような状況にあれば、会社の実績に当事者意識を持つレベルの悪化がない限り、あえて変化点を作ろうとはしないのは自然なことです。
このように会社の役割や実績が安定すると、組織内での循環がない会社。いわゆる会社の衰退期へと突入し、到底生産的とは思えないような事柄が当然のように起きるのです。
変化を嫌う会社の処方薬

変化を嫌う会社を変える処方薬は、実のところ劇薬しかありません。それは前述したように、経営者の役割である会社の実績が、当事者意識を持つほどに悪化することです。
しかし一度業績の悪化が起きれば、それを改善することは容易ではありません。そのような状況に陥る前に、本来であれば株主が会社側に意見するべきですが、日本の株主は会社への関与が少ない傾向があります。
株主による組織改革の可能性
資本主義において、会社は株主への還元を目的とする集団と定義されます。欧米諸国では株主の権限が強く、企業経営に対する積極的な関与が一般的です。
株主は第3者目線から会社の利益となる指示を出すことができ、会社の新陳代謝を上げる役割を担えますが、日本においてはそれを反映できていないのが実情です。
日本の株主の優位性が低い要因
- 株主提案権の行使要件の厳しさ:日本では株主が議題提案を行うための要件が厳しく制限されています。
- 株主総会の形式的運営:株主総会は形式的な運営となる場合が多く、株主からの指示が無いこともあります。
- 長期コミットメント主義:短期的なコミットを目的とする株主の意見は経営に反映されにくい特徴があります。
近年では日本でもコーポレートガバナンス改革が進められ、株主の役割強化が図られていますが、依然として他国と比べると株主の指示や関与の頻度は低い状況が続いています。
業績悪化による改善の可能性
業績の悪化により社内改革を行なった結果、悪化前より業績が伸びた事例は少なくありません。
しかし多くの会社は、経営者やそれに準ずる役職者が入れ替わることが多く、経営方針の変化から会社員は以前の働き方を継続するのは難しくなる可能性があります。
業績改善に成功した事例
日本航空株式会社(JAL):経営破綻後、稲盛和夫氏を会長に迎え「アメーバ経営」を導入。社員一人ひとりが経営に参加し、収支管理を可視化することで、わずか6年で業績を急回復させました。
レゴ(LEGO):業績不振の後、CEOに就任したヨアン・ヴィー・クヌッドストープ氏(現ブランドグループ会長)は、原点に立ち帰りレゴらしさを取り戻すことに注力。業績をV字回復させました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ):開業後の業績不振により、森岡毅氏がチーフ・マーケティング・オフィサー(CMO)として就任。数々のマーケティング戦略を展開し、V字回復を遂げました。
変化を嫌う会社で会社員がやるべきこと

会社員がやるべきは、所属している会社の改善を図ることではなく、自身の環境を変化させることです。現代では転職により給与を上げる人も多いですが、個人的には副業をすることをおすすめします。
副業をすることの重要性
例えば現在の待遇に対して不満がある場合には、より即効性の高い転職がおすすめできます。しかし変化しない会社に対して将来性に不安を持つ会社員にとって、即効性の優先順位は高くありません。
対して将来性の低さと相性が良いのは、将来性の高さを特徴とする副業です。副業には以下のような複合的なメリットも存在します。
- 現在の待遇を落とすリスクを回避できる。
- 転職では得られないメリットが存在する。
- 継続して成功すれば独立も可能。
- 本業の会社に依存しない人材となれる。
- 個人で確定申告をする必要がある為、簿記スキルが学べる。
- 稼げる金額が青天井の為、本業の年収を超える場合も珍しくない。
- 総じてITやSNS、生成AIの活用が必要なシーンが多くある為、それらの知識が取得できる。
転職と比較して即効性が無いデメリットは存在しますが、継続すればするほどその過程が自信となり、スキル・自信・複数の収入の柱を全て持つことができます。
副業については以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

最後に
今回は変化を嫌う会社をテーマとし、その改善方法や会社員が取るべき対策についてご紹介しました。
会社におけるほとんどの問題は会社組織、いわゆる人間関係によって起きます。そのような事象は個人レベルでの改善は難しく、更に会社員が業績の悪化を作ること自体、倫理的な問題が発生します。
会社に対して不満がある場合、その会社に対して意見するのではなく、自身の環境を変えることに注力することが重要です。自分に決定権があるものは何かを認識し、できることに時間を費やしましょう。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。




