私は現役で商社の営業マンをしています。産業設備や建設・インフラ関連の商材を取り扱う商社では、取引先へ依頼した工事の立会を行うことが多々あります。
工事自体に馴染みがない人にとっては、工事立会の内容や必要性について答えられる人は少ないと思います。その一方で、特にハードが強い日本においては工事を行う業界は多岐に渡り、知っておいて損はない分野とも言えます。
今回は、今後工事に関係する業界で働く予定がある人や、現在働いているが何の為に工事立会があるのかわからない人に向けて、その詳細と必要性についてご紹介します。

- 工事立会の概要や必要性に対して疑問を持っている人
- 工事の立会者を探しているが、どのような人が適材かわからない人
 新野くん
新野くん工事立会をしている人って作業せずにずっと立ってる印象だけど、彼らにも役目があるのかな?
 くろひつじ
くろひつじもちろんだメン!工事立会は元請が行う場合が多いけど、その工事の安全や進捗、商品の品質に責任を持つ役割があるんだ。
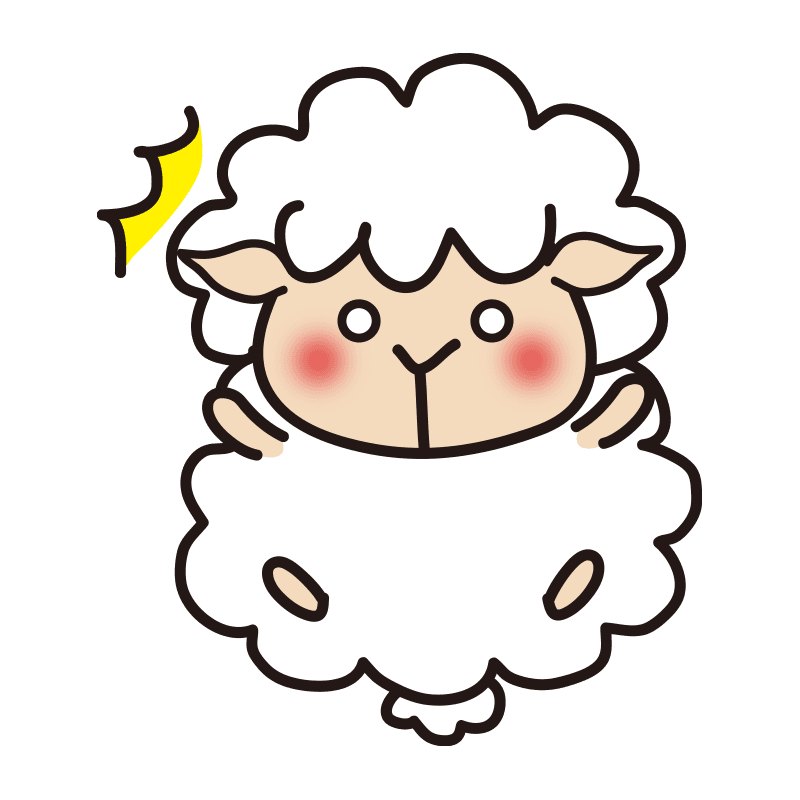
- 工事立会の役割とは、元請が担う役割の一部である。
- 重層下請構造の要因には、餅は餅屋理論と元請のリソース不足が関係している。
- 元請のリソース不足を解消する方法は、工事立会時に現場代理人を委任することである。
それぞれの役割
まず本章では、元請と下請それぞれが担う役割についてご紹介します。産業設備や建設・インフラ等の工事を頻繁に行う業界では、必ず顧客が手配する元請と、元請が手配する下請が存在します。
例えば「三次下請業者」が工事を行う場合、それぞれの関係者は建設業法、労働安全衛生法、元請・下請契約、現場ルール等に基づいて明確に役割が分担されます。

元請業者
主な役割:工事全体の管理責任者
- 全体の工程・品質・安全を管理。
- 下請業者との契約、指導、監督を行う。
- 労働安全衛生法に基づく「統括安全衛生責任者」としての責任を担う。
- 作業間調整、安全教育、災害防止協議会の運営。
一次下請業者
主な役割:自社作業と二次下請業者の管理
- 元請との契約に基づき、特定の工程を担当。
- 二次業者への発注、作業指示、現場調整。
- 自社と二次業者の作業員に対する安全教育、指導。
二次下請業者
主な役割:同上
三次下請業者
主な役割:現場での実際の作業を担当
- 二次業者からの指示に基づいて工事を実施。
- 現場の安全ルール、作業手順、品質基準に従う。
- 作業前ミーティングへの参加。
- 作業日報や進捗報告、安全教育の受講。
重層下請構造の要因
このような重層下請構造の場合、下請業者の数が増える程顧客のコストが増加し、対して増加した分の費用は最下層である三次下請に還元される分が少なくなります。
建設業法第24条の7においても「重層下請構造の是正」が求められており、この構造は原則として避けるべきものとされています。では何故、このように是正されている現代でも、重層下請構造が無くならないのでしょうか。
本章では、この構造が日本に根差している理由をご紹介します。
餅は餅屋理論
重層下請構造となっている理由の一つが餅は餅屋理論です。例えば顧客が元請に産業設備を手配した場合、以下のような作業が発生し、それぞれの作業で対応できる業者が異なります。
| 作業 | 対応者 | 会社 |
| 顧客の要望をヒヤリングする | 営業 | 元請 |
| 設備を設計する | 設計 | 設備メーカー |
| 購入品を手配する | 購買 | 設備メーカー |
| 支給品を手配する | 営業 | 元請 |
| 支給品を運搬する | 運搬業者 | 下請 |
| 設備を製作する | 製造 | 設備メーカー |
| 設備を調整する | 品質 | 設備メーカー |
| 設備をバラす | 製造 | 設備メーカー |
| 設備を運搬する | 運搬業者 | 下請 |
| 設備を横引きする | 重機業者 | 下請 |
| 導入箇所の清掃をする | 清掃業者 | 下請 |
| 導入箇所のケガキをする | ケガキ業者 | 下請 |
| 導入箇所へエア配管や電気配管を延長する | 配管業者 | 下請 |
| 導入箇所へエア配線や電気配線を延長する | 配線業者 | 下請 |
| 導入箇所へ通信ケーブルを延長する | 通信業者 | 下請 |
| 設備を復旧する | 製造 | 設備メーカー |
| 設備を精度調整する | 品質 | 設備メーカー |
 くろひつじ
くろひつじめちゃくちゃいっぱいあるね~。
産業設備を導入するだけで、このような多岐に渡るタスクが存在します。上記は設備メーカーが自社で設計・製造・品質・購買を抱える場合ですが、もしそれが無い場合には元請がさらにその専門業者を手配します。
もし元請がこれらすべての作業を一次下請として手配すれば、政府の言う「重層下請構造の是正」が実現可能ですが、元請は通常複数の工事を抱えており、そのリソース不足から下請の数をできるだけ少なくするのが実情です。
- 支給品とは?
- 元請が下請に渡す部品や材料を指します。下請が購入すると金額が上がってしまう場合や、下請が商品を購入できない(口座がない等)場合に元請が購入し、下請に支給します。
- 横引きとは?
- 納入先で横方向に重量物を運ぶ作業を指します。顧客の工場で運搬する場合は重機等を用いてその工場内で横引きし、設置箇所に運搬します。
- ケガキとは?
- 納入場所の床に予め線や点を描く作業を指します。精密加工機等は設置場所が数ミリ単位でズレると生産品に影響が出る為、予め基準線や穴あけの位置を描いた上で設置します。
元請のリソース不足
前述した元請が複数の工事を掛け持ちする理由は、物件毎の粗利率が関係しています。当然ながら、顧客へ出した見積もりは相見積もりとなり、通常は競合との価格差で依頼先が決まります。
業界平均の粗利率は10%であり、これを超えれば競合に価格差で負けてしまう為、組織運営が難しい粗利率で工事を請負し、それを複数の物件で埋めることで、重層下請構造が成立せざるを得ない状況を招いてしまうのです。
解決策
このような状況を是正するには、元請のリソースを軽減するか、下請の餅は餅屋理論を是正するかのどちらかになります。
しかし、下請が作業範囲の拡大を図る場合にはそれに準ずる資本力が必要であり、また元請のリソース不足は日本特有の企業文化も関係している為、個人レベルでの解決は難しいのが実情です。
日本企業の課題については下記ブログでもご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

工事立会者の役割

さて、次に工事立会者の役割を見てみましょう。ここで言う立会者とは、工事監督者を指しています。
一般的に工事立会は元請の役割として認識されますが、工事は長期連休等の長期間に及ぶケースが多く、元請がそこにリソースを投下できないことが多々あります。
工事立会者と元請の役割
そこで考えたいのが、元請の役割と工事立会者の役割は同じ関係性にあるかどうかです。工事立会者は、工事の進行中に現場での安全・品質・進捗確認を行う役割を担います。具体的な職務内容は以下の通りです。
主な役割:工事の安全・品質・進捗を確認
- 安全管理:現場の安全対策が適切に実施されているかを確認し、労働災害の防止に努めます。
- 品質管理:施工が設計図や仕様書に基づいて正確に行われているかを確認します。
- 進捗管理:工事が計画通りのスケジュールで進行しているかを監督し、必要に応じて調整を行います。
一見すれば元請と立会者の役割は一貫していると思われますが、実際には工事の時しか立会者の役割は発生しません。ここで例えば現場代理人を委任すれば、元請の役割である工事立会のタスクを省くことができます。
現場代理人の可能性
現場代理人とは、元請業者の代表として工事現場での全権を委任された者で、発注者との交渉や契約履行の責任を持ちます。
建設業界以外ではあまり認知度は高くありませんが、現場代理人を立てれば工事立会を委託でき、元請は他の役割である受注活動や中間管理にリソースを集中することができます。
本ブログの運営元である新野商事でも、この現場代理人の派遣事業を行なっています。

工事立会がある業界
本章では、具体的に工事立会がある業界についてご紹介します。日本において工事立会が行われる業界は複数あり、以下の業界で工事立会が制度化・慣習化されています。
建設業
立会者:元請、監理技術者、施工管理技士
- 公共工事・民間工事を問わず、工事の中間・完成時に立会が必要。
- 検査対象:基礎、鉄筋、配筋、防水、引渡し時の仕上げ等。
- 特に国や自治体が発注する公共工事では、検査要領に立会が必須と規定されている。
インフラ業
立会者:東京電力、東京ガス、水道局等のインフラ会社
- 電柱設置、電線引込、ガス配管、水道管接続の際に、供給事業者の立会が義務付けられている。
- 安全性・規格・漏れチェックが主目的。
- 接続前検査・通電/通水検査等で立会実施。
情報通信業
立会者:通信事業者または管理会社
- 建物への光回線引込や基地局設置等の際、通信会社側の立会が必要。
- 特に集合住宅・商業施設で管理会社との調整が必要なケース多数。
交通インフラ業
立会者:道路管理者、鉄道事業者、警察
- 鉄道敷設、踏切工事、道路下横断工事。
- 占用許可を得た上で、立会による安全確認や復旧検査が義務付。
- 特に地下埋設物(ガス管・上下水道等)が絡む場合、関係機関が立会。
工場・建設・設備業
立会者:元請、安全管理者
- 石油、化学、製鉄、食品等のプラントにおける機器据付・配管工事。
- 品質チェックや安全基準遵守の為、施工中・完成時に立会が行われる。
- 溶接検査、無災害記録の確認、ISO管理項目のチェックも含まれる。
住宅リフォーム・不動産業
立会者:施主、管理会社、施工業者
- クロス貼替、床張替え、水回り工事。
- 完成時や中間工程での立会確認が一般的。
- 特に賃貸物件では管理会社の立会が入るケースが多い。
最後に
今回は、今後工事に関係する業界で働く予定がある人や、現在働いているが何の為に工事立会があるのかわからない人に向けて、工事立会の詳細と必要性についてご紹介しました。
日本では「重層下請構造の是正」が求められていますが、元請のリソース不足と下請の餅は餅屋理論から、現実には反映が難しい状況が続いています。
しかしそんな中でも、各事業者のサービスは日々進化しており、全体の商売にアンテナを張れば解決策は必ず存在します。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。




