皆さんは何かを決定する際、直感と論理どちらで決めていますか。
私は現役で商社の営業マンをしています。商社に限らず、仕事の現場で起こる選択には、常にリスクと責任が付き纏います。
そしてリスクとリターンは表裏一体であり、適正なリスクをとることが、自分や組織の目標達成に繋がります。
今回は、選択に意味を持たすために必要な「期待値の計算式」と、その活用方法についてご紹介します。

- 選択に責任を伴う立場の人
- 組織における選択を論理的に行いたい人
 新野くん
新野くん期待値って仕事の現場ではあまり聞かないね。確かに選択する機会は多いけど、いつも直感的に判断してるなあ。
 くろひつじ
くろひつじメン!直感的に判断することは悪いことじゃないよ。期待値の計算は、その選択をした理由を論理的に説明するモノだからね。
重大な決断をした結果、失敗することは決して悪いことではありません。
一方で、過去に成功体験を積み上げた人ほど、その選択には責任が伴います。また組織における選択も、全員が納得する理由を説明するのは想像より難しいものです。
その判断基準は人により異なるのも当然ですが、時に明らかな正解がある場合でも、選択者の心理状態で結果が変化することもあるのです。
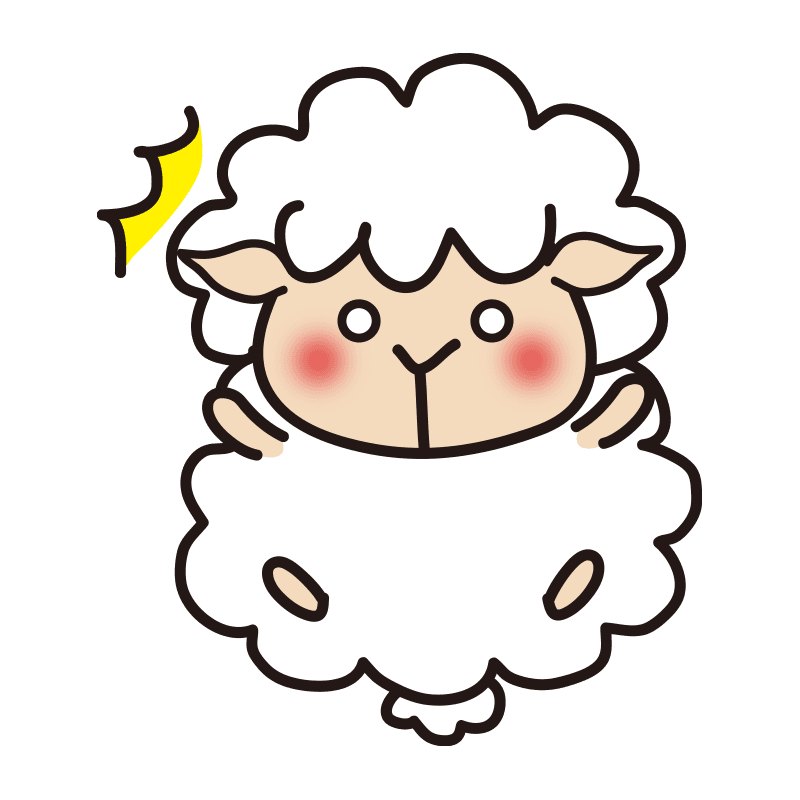
- 個人的な選択をする場合には、リスク軽減が重要である。
- 組織的な選択をする場合には、計算材料の信憑性が重要である。
- 選択した結果は例外なく結果論である。選択したことを信じ進み続ける必要がある。
選択の概要

成功者の多いユダヤ人の書物タルムードには、選択の重要性を示す逸話が数多く残されています。「ふたつの道」もその1つです。
ふたつの道
ある男が旅をしていました。道が二つに分かれる場所に差し掛かり、どちらの道を進むべきか迷っていました。そこに一人の賢者に出会い、男は尋ねました。「どちらの道を行くのが正しいのでしょうか?」
賢者は答えました。「どちらの道も、最初は険しく困難だろう。しかし、一方の道を選び、最後まで歩き抜いた者には、必ずや安寧と喜びが待っている。もう一方の道を選び、途中で諦めてしまった者には、後悔と失望しか残らないだろう。」
男は深く考えました。そして、一方の道を選び、困難に立ち向かいながらも歩き続けました。時には挫けそうになりながらも、賢者の言葉を信じて進みました。長い年月が過ぎ、男はついに目的地にたどり着きました。そこには、彼が想像もしなかったほどの幸福と平和が待っていました。
一方、もう一つの道を選んだ別の男は、最初の困難に直面しただけで諦めてしまいました。彼は別の道を探し、また別の道へと移りましたが、結局どこにもたどり着くことはできず、後悔の念に苛まれながら人生を終えました。
この物語には複数のメッセージが込められています。
まず、この2つは同じ道であった可能性があります。自身の選択を正しいものにするには、選択した道を進み続けなければいけません。
次に、選択した結果はすべて結果論であることです。
例え賢者の助言であっても、選択した時点でそれが正しいか証明することは誰にもできません。だからこそ、組織が同じ選択するためには、トップダウンやボトムアップといったルールが必要なのです。

タルムードとは、ユダヤ教の律法と倫理・哲学・物語・伝承を集めた文書集を指します。翻訳版は誤訳の可能性があるため、ヘブライ語で書かれたものが聖典とされています。
タルムードの教えについては以下のブログでご紹介しておりますので、ぜひ合わせてお読みください。

人生は選択の連続
「人生は選択の連続である」という考えは、多くの分野で提唱されています。
- 心理学:アメリカ心理学会(APA)
- 人は1日に平均3万5,000回の意思決定をしていると推計。
- 哲学:実存主義のサルトル氏
- 人間のあらゆる行為は選択によって成り立つと主張。「選択の放棄すら選択である」
- 行動経済学:ノーベル賞を受賞したダニエル・カーネマン氏
- 人間の生活には無意識的な「小さな選択」が連続して起きていると主張。
選択疲れ
アメリカの心理学者ロイ・バウマイスター氏は、人間は1日のうちに何度も選択を繰り返すことで、選択疲れを起こす(自己制御力が低下する)ことを提唱しました。
ショッピングで選択肢を次々に選んだ被験者は、その後のテストで自己制御力が低下することが実験で確認された。
経営者やリーダーは、重要な意思決定を午前中に済ませることを推奨。
オバマ元大統領が「服の色を毎日同じにする」のは決定疲れを避ける有名な例。
期待値の計算式

例えば大企業・中小企業・個人のそれぞれが、どの新規事業に参入するか選択する場合を考えてみましょう。
 くろひつじ
くろひつじビジネスの期待値は以下のような方程式になるよ!
期待値=成功確率×利益+失敗確率×損失
期待値(年間)=期待値÷継続年数
選択者
- 大企業
- 資本金:5億円以上
- 従業員数:100名以上
- 中小企業
- 資本金:3億円以下
- 従業員数:100名以下
- 個人
- 資産:1000万以下
新規事業
A案
成功確率:30%、平均利益:1億円
失敗確率:70%、平均損失:-3,000万円
平均継続年数:3年
B案
成功確率:10%、平均利益:10億円
失敗確率:90%、平均損失:-5億円
平均継続年数:3年
C案
成功確率:30%、平均利益:1,000万円
失敗確率:70%、平均損失:-100万円
平均継続年数:10年
D案
成功確率:10%、平均利益:1億円
失敗確率:90%、平均損失:-1,000万円
平均継続年数:10年
計算結果
A案
期待値:0.3×1億+0.7×(−3,000万)=900万円/3年
年間の期待値:900万÷3= 300万円
B案
期待値:0.1×10億+0.9×(−5億)=−3.5億円/3年
年間の期待値:−3.5億÷3= −1.17億円
C案
期待値:0.3×1,000万+0.7×(−100万)=230万円/10年
年間の期待値:230万÷10= 23万円
D案
期待値:0.1×1億+0.9×(−1,000万)=100万円/10年
年間の期待値:100万÷10= 10万円
選択条件
ビジネスにおける期待値の計算には、情報の精度とリスク低減が必要になります。
A~D案の精度は正しいものとする。
これは特に組織において重要な選択をする場合に必要な要素です。
情報の精度とは、上記A案~D案のような期待される結果を統計学的に図ることを指します。統計学上、最低400のサンプル数が必要となるため、専門の会社へ依頼しましょう。
リスク低減を考慮する。
これは特に個人において重要な選択をする場合に必要な要素です。
個人の選択で期待値より優先されるのはリスク低減。失敗した時に再度挑戦できるリスクに抑えることです。固定費の概念がない個人であれば、失敗するリスクよりも失敗する前提で捉えるべきです。
選択結果
以上の条件から、それぞれの推奨される選択は以下になります。
| 区分 | 推奨案 | 理由 |
|---|---|---|
| 大企業 | A案 | B案はハイリターンであっても期待値がマイナスのため、A案。 |
| 中小企業 | A案 | 損失3,000万円に耐えられる場合はA案。耐えられない場合はC案。 |
| 個人 | C案 | D案はハイリターンであっても期待値が低いため、C案。 |
最後に
今回は、選択に意味を持たすために必要な「期待値の計算式」と、その活用方法についてご紹介しました。
組織において何かを選択をすることは、反対意見を持つ人からの軋轢を生みます。いくら情報の精度を上げて論理的な説明をしても、それが正しいと証明するのは結果を出した後になるのです。
一方で自由とは、自分が選択権を持つことを意味します。人の選択を否定することや、自分が選択することを面倒がるのは何のメリットもありません。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。




