私は現役で商社の営業マンをしています。主にB2Bの商売では、取引先から見積書を貰うことや、提出する機会が頻繁にあります。受け取った見積書は自社で手配処理、もしくは上乗せした価格で顧客へ提出します。
前者である手配処理をする際には、事前に商品の相場リサーチや人件費チャージの確認、全体に対する諸経費の比率を算出し、その適正価格を判断します。
後者である顧客へ提出する際には上述した内容の他に、相場許容範囲内の価格を上乗せし提出します。取引先によって見積書のフォーマットは違えども、基本的な考え方はどの見積書も統一しています。
今回は、今後B2Bの商売をする会社へ入社する方や、現在入社しているが見積書の作り方がわからない方に向けて、その具体的な概念と上乗せする方法をご紹介します。

- 今後B2Bの商売をする会社へ入社する人
- 現在B2Bの取引をしているが見積書の作り方がわからない人
 新野くん
新野くん適正な見積書を作るのって難しいんだよね、、先輩はすぐ要点を絞るから、その方法を知りたいのにマニュアルも無いし。
 くろひつじ
くろひつじメン!そうだね。見積書の作り方は言語化が難しいから、決められたマニュアルが無い会社も多いんだ。
大手メーカーは見積書を作成する際、名称を入力すれば金額も自動入力される見積システムを導入していることもありますが、一般的な会社にはそのようなシステムは存在していません。
一方で、マニュアルさえも無い会社が多く、仕入れ値に対してどの比率で価格を設定するのが適正か、その項目毎に上司に確認を取る営業も少なくありません。
ある程度の数をこなせば適正価格は感覚で身に付くものですが、その実は会社依存ではなく業界平均から割り出した価格であり、他社の営業から学ぶことが十分可能な分野でもあるのです。
そのような共有可能な概念に時間を取られ、結果として生産性を落とすことは好ましくなく、今回はその要点をご紹介できればと思います。
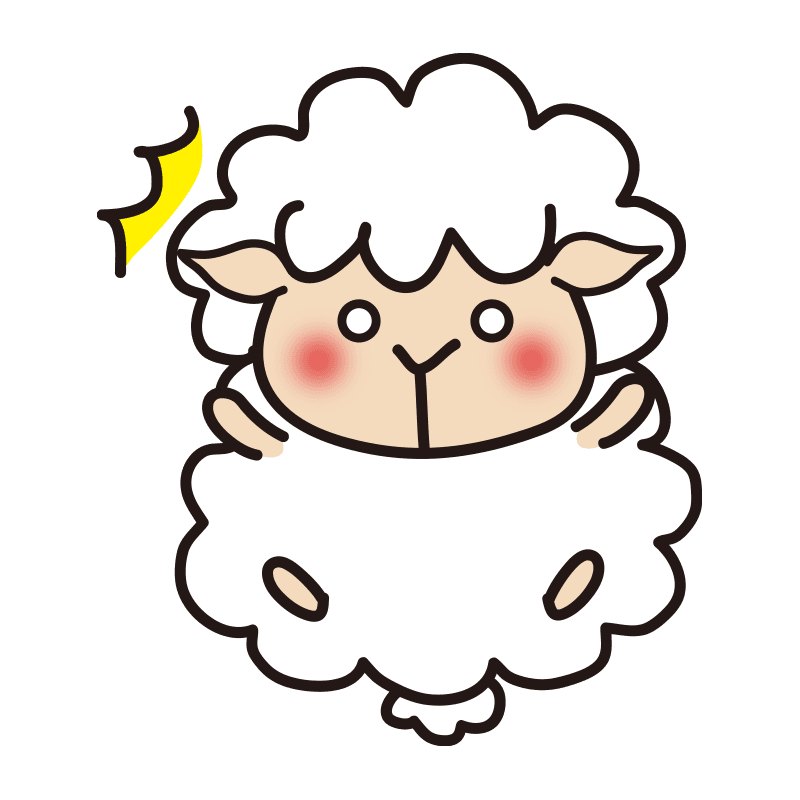
- 商品の適正価格は、商流の無いものは5~10%、商流があるものは15~20%である。
- 人件費の適正価格は、項目毎のチャージ金額と業界平均を照らし合わせた価格である。
- 諸経費の適正価格は、管理費は10%、パッケージとその他の項目は常識の範囲内で設定する。
値付けの前提
B2B取引における値付けの前提は、最悪の可能性を考慮し極端に高い粗利設定はしないこと。及び型式をあえて記載しない等の不誠実なことはしないことです。これは顧客からの信頼は一時の利益に勝ることを意味します。
実績価格を調べる
見積書を受け取ったら、まず自社の手配実績、もしくは販売実績を確認します。適正価格云々より、実績があればその価格に則る必要があるからです。
例えば自社が顧客に見積書を提出する際、その時々によって価格が変動していれば、顧客からの信頼が損なわれます。もし実績価格と異なる金額になる場合、相応の理由を事前に顧客へ説明しましょう。

- 材料費が上昇した。
- 仕入先が人件費の見直しを行なった。
- 廃業や倒産により、仕入先が変わった。
- 要求仕様が一部異なり完全なリピートではない。
- 納期を短縮する為、一部の作業を外注へ依頼する。
商品の適正価格

まずは商品の適正価格について見てみましょう。ここで言う商品とは、有形物である部品や材料を指します。
見積書における商品とは、大きく分けて購入品と制作品の2種類に分類できます。業界におけるその商品の相場と、その商品が購入品と制作品どちらに分類されるかで適正価格が異なります。
購入品
購入品とは、その名の通り他社から購入したものを指します。
購入元が例えばモノタロウやミスミであれば、見積書に型式を記載すれば顧客もその仕入れ値を知ることができます。その場合、乗せれる金額は会社の最低粗利(一般的に5%)となるでしょう。
またその購入元がEC未参入のメーカーであった場合でも、競合が見積書を取得できるメーカーであれば、自社の粗利率を顧客が知り得る可能性があります。
よって、購入品のほとんどは仕入れ値に対する粗利率5%~10%が適正であると言えます。

粗利率とは、売上高に対する粗利益の割合を示す指標です。
・粗利益の計算式:粗利益=売上高-原価
・粗利率の計算式:粗利率(%)=粗利益÷売上高×100
制作品
制作品とは、発注するメーカーもしくはその下請が制作する商品を指します。こちらも同じように競合が見積書を取得できるメーカーであれば、粗利率は高くても10%に抑えるべきです。
しかし、これが商流のあるメーカーであれば話が変わります。商流とは商いの流れを意味し、競合が見積書を取得することができません。
このような商品は顧客が仕入れ値を把握することができない為、適正粗利率が15%~20%まで跳ね上がります。商流については以下のブログでご紹介していますので、ぜひ合わせてご参考ください。

【早見表】仕入れ値に粗利益を乗せる計算式
| 粗利率 | 計算式 |
| 5% | 売価=仕入れ値÷0.95 |
| 10% | 売価=仕入れ値÷0.9 |
| 15% | 売価=仕入れ値÷0.85 |
| 20% | 売価=仕入れ値÷0.8 |
| 25% | 売価=仕入れ値÷0.75 |
| 30% | 売価=仕入れ値÷0.7 |
人件費チャージの適正価格

人件費チャージとは、時間もしくは日当たりの人件費を指します。日数や人数を見積書に記載しない場合もありますが、メーカーは必ず見積段階で計算していますので、問い合わせれば教えてくれます。
具体例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作業費 | 400,000円 |
| 作業人数 | 4人 |
| 作業日数 | 2日間 |
| 人件費チャージ(1人/日) | 400,000円 ÷ 4人 ÷ 2日間 = 50,000円 |
| 人件費チャージ(1人/時間) | 50,000円 ÷ 8時間 = 6,250円 |
業界毎の平均値
割り出した人件費チャージが適正か判断するには、その業界の平均値を考慮する必要があります。一般的に技術力の求められる業界程、チャージ金額が高い傾向にあります。
コンサルティング業界
- 経営コンサルタント:約10万円~30万円/日
- 戦略立案や業務改善を行うコンサルタントの報酬は高額になる傾向があります。
IT・システム開発業界
- プロジェクトマネージャー:約8万円~13万円/日
- プロジェクト全体を管理するPMの単価は高めです。
- システムエンジニア:約5万円~10万円/日
- 設計や開発を担当するSEの単価は経験やスキルにより変動します。
- プログラマー:約4万円~8万円/日
- コーディングを担当するPGの単価は比較的低めです。
自動車産業
- 技術者・エンジニア:約5万円~10万円/日
- 専門的な技術を要するエンジニアの単価は高めです。
建設業界
- 施工管理技士:約3万円~6万円/日
- 現場監督や施工管理を行う技士の単価は経験や資格により変動します。
もし見積書に記載されているチャージ金額が業界平均より高い場合には、その理由をメーカーへ問い合わせましょう。
営業によっては、このチャージ金額に諸経費(宿泊費や交通費等)を含んでいるケースもありますが、その場合は後述する諸経費の項目が少なくなります。
人件費の種類
次に、見積書のどの項目が人件費に当たるのか見てみましょう。基本的には、その名の通り従業員の労務を連想されるものは全て該当します。
| 項目 | 種類 |
| 設計費 | メカ設計・電気設計・ソフト設計 |
| 開発費 | メカ開発・電気開発・ソフト開発 |
| 作業費 | 現地作業費・社内作業費 |
| 調査費 | 現地調査費・社内調査費 |
| 調整費 | 現地調整費・社内調整費 |
| 制作費 | 現地制作費・社内制作費 |
| 組立費 | 現地組立費・社内組立費 |
| 配線費 | 一次配線・二次配線 |
これらのチャージ金額は全て同額という訳ではなく、例えば設計費はメカ・電気・ソフトそれぞれでチャージ金額が異なることもあります。
重要なのはチャージ金額を合わせることではなく整合性を成り立たせることであり、そのメーカーや種類毎にチャージ金額を決め、実績金額を合わせることが必要になります。
諸経費の適正価格

諸経費とは、上述した商品や人件費以外の項目を指します。またパッケージもこの項目に含まれており、例えば廃棄費用は労務を連想させるものの、一般的に重量に対して価格が決められている為諸経費に該当します。
また移動拘束費は労務では無く諸経費に当たりますが、人件費チャージのように時間単価を割り出せるように設定する必要があります。

見積書におけるパッケージとは、予め価格が決められているものを指します。例えば点検作業は労務を連想させますが、点検内容と金額が決められている場合はパッケージに該当します。
パッケージは商品や人件費のように単価を割り出すことができません。しかしその分、仕入先は残業が発生した場合の追加費用請求もできないという特徴があります。
諸経費の種類
| 項目 | 詳細 |
| 交通費 | 出向先への交通費 |
| 移動拘束費 | 移動中の拘束時間 |
| 宿泊費 | 人数と日数を記載 |
| リース費 | 必要資材のリース費用 |
| 図面・取説費 | 書類作成に必要な用紙・インク代 |
| 管理費 | 一般的に全体金額の10%前後で設定 |
商品と同じく管理費に関しても相場がある程度決まっており、粗利率は高くても10%に抑えましょう。
相見積と一社選定
さて、以上が見積書に関する知識と適正価格になりますが、次に営業が知っておくべき見積の概要について見てみましょう。見積には、競合のいる相見積と、競合のいない一社選定の2種類があります。
相見積
複数の会社で同じ仕様の見積を提出し、その価格差で依頼先を決めます。相見積をする会社の数は、得意先の規模にもよりますが、一般的に0~数百万円の案件は2社、1000万円以上となると3社になる場合もあります。
依頼先へ要求する仕様内容は共通で、仕様を満たさなければ競合先とは認められません。商社では競合先に選ばれることを土俵に乗ると表現します。イメージは相撲における土俵と同じです。
異なる商社が同じメーカーで相見積をする場合もあれば、異なる商社が異なるメーカーで相見積する場合もあります。但し、前者はメーカー側が複数の商社へ見積を提出することを了承する場合に限定されます。
相見積の一般的な流れは以下の通りです。
得意先の担当者が商社へ見積依頼をします。商社は依頼を受けたら、依頼内容や仕様書をメーカーへ展開します。商社は自社に商流のあるところからメーカーを選定する場合もあれば、そもそも得意先からメーカー指定がある場合もあります。
要求仕様は総じて複雑な為、仕様書に対し質問点が出たり、漠然とした表現になっていたりする場合が多々あります。その為、Webや面直などで3社(得意先、商社、メーカー)で要求仕様の擦り合わせを行います。商社はこれをキックオフMTと呼びます。
商社から得意先の担当者へ見積を提出します。担当者は自社の承認を得た後、購買部門に見積を上げます。相見積の場合、担当者はこの流れを競合の数だけそれぞれで行う必要があります。
すべての商社から見積が揃った段階で、購買は商社へ入札見積の提出を依頼します。入札見積は公平性の観点から、郵送で、かつ未開封のものでしか認められません。入札見積が揃ったら、購買は各社の見積を同時に開封し依頼先を決定します。

入札見積とは、担当者へ提出した見積から値引きをした見積書を指します。入札は安い方に依頼先が決定する為、商社は取りたい案件程より多く値引きします。当然ながら、各社がいくら値引きしたかは開封するまで分かりません。
一社選定
一社選定とは、上述したステップの競合がいないパターンで、得意先の購買は入札見積は依頼せず最終見積の提出を商社へ依頼します。競合がいない一社選定は以下の条件に該当する必要があります。
- 既に導入済みの商品・サービスと同等のものを依頼する場合。
- 既に導入済みの商品・サービスの修理、改善、改造、かつ他社では実施不可の場合。
- 上記いずれかに該当し、かつメーカーが導入時に仲介した商社にしか見積を出さない場合。
つまり、他のメーカーでは要求仕様を満たせない場合、かつそのメーカーが導入時の商社にしか見積を出さない場合は一社選定となります。
商社やメーカーはすべての案件が相見積になってしまうと、十分な利益を出せません。しかし導入した商品やサービスに関する情報を開示しなければ、更新、修理、改善、改造が必要な際は一社選定にすることができます。
よって、多くのメーカーは自社の商品やサービスに関する情報は開示せず、かつ商流のある商社にしか見積を出しません。
相見積に勝つ方法については以下のブログでご紹介しておりますので、是非合わせてお読みください。

最後に
今回は、今後B2Bの商売をする会社へ入社する方や、現在入社しているが見積書の作り方がわからない方に向けて、その具体的な概念と上乗せする方法をご紹介しました。
見積書の正当性はその会社の信頼に直結する為、その作り方は営業にとって重要な役割の一つであると言えます。
見積の内容によって営業実績が向上する訳ではありませんが、正当性が無い場合マイナス面には作用する為、十分に注意が必要です。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。



