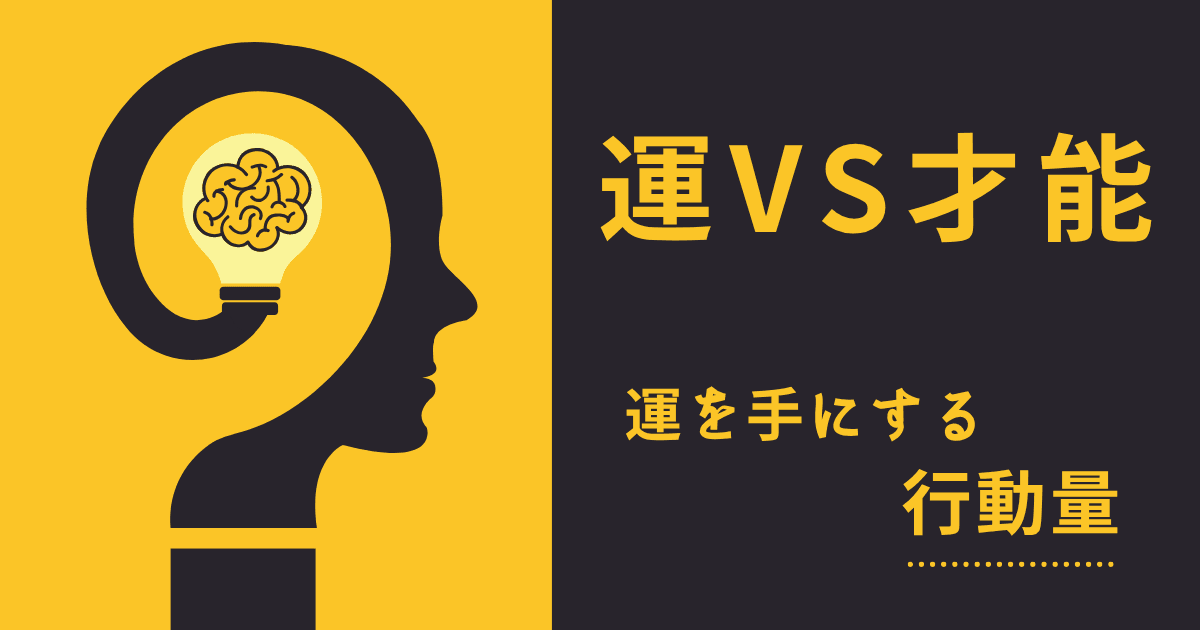皆さんは、成功するうえで「運と才能」どちらの要素が大きいと思いますか。
私は現役で商社の営業マンをしています。この課題に関して研究を行い、2022年にイグノーベル経済学賞を受賞したのが『才能と運:成功と失敗におけるランダム性の役割』です。
今回は本研究テーマを基に、成功に必要な「運と才能」それぞれの比重の違いや、運を呼び寄せる『行動量』の重要性についてご紹介します。

- 成功者のビジネス書に再現性があるか疑問な人
- 運を呼び寄せる方法について知りたい人
 新野くん
新野くん一見すると才能の方が比重が高い気がするけど。でなければビジネス書の存在意義が無くならない?
 くろひつじ
くろひつじメン!そうだね。けど残念ながら、運の比重の方が圧倒的に高い結果になったんだ。
結論から言うと、「運と才能」は相関関係があるのの、運に恵まれなければほぼ成功できないという構造が本研究で明らかになっています。
但し、この『才能』とは資産の相乗効果を示しており、実社会において重要な『行動量』は含まれてはいません。
まずはイグノーベル賞の概要から、シミュレーション研究のモデル設定を具体的に見ていきましょう。
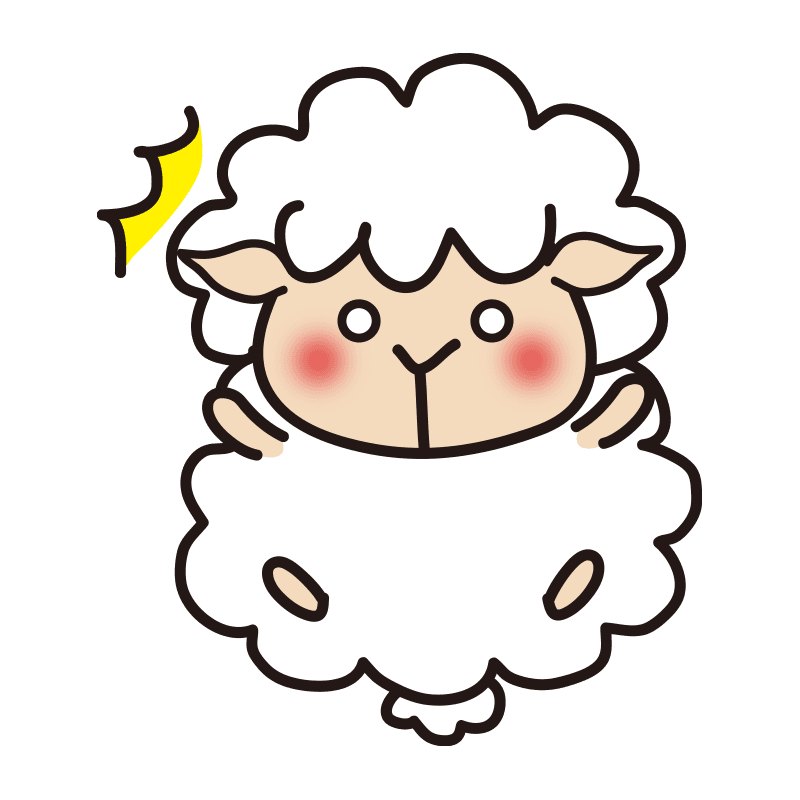
- 本研究の結果、成功者上位10人の平均才能値は中位層となった。
- そして才能差があまり無くても、成功差は極端に広がる傾向がある。
- 但し本研究に『行動量』は反映されておらず、これが『運を手にする方法』である。
イグノーベル賞とは?
イグノーベル賞とは『笑い、そして考えさせる』ユーモアと科学を融合させた賞であり、ノーベル賞のパロディとして1991年に創設されました。
単なるジョークではなく、一見風変わりでも深い洞察を含む研究テーマに本賞は贈られます。
 くろひつじ
くろひつじ今回の受賞理由も、単なる話題づくりではなく、現代社会の『実力主義』に異議を唱える強い示唆があったんだ。
研究内容
201×201の盤面に1,000人のエージェント(人間)を配置し、各エージェントの保有資産額が、40年間でどのように推移するかをシミュレーションしました。
モデル設定
- 才能値:0~1のランダムな値で、1,000人の平均値は約0.6。
- 初期資産額:全員一律で『10ユニット』からスタート。
- 寿命:20~60歳(40年間)を想定。
 くろひつじ
くろひつじこの研究における成功は、40年後の保有資産額(単位:ユニット)の多さを定義しているんだ。
またライフイベントとして、『運の良いイベント』と『運の悪いイベント』が発生するよう設定します。
イベント数は40年間で各250回(合計500回)発生し、タイミングや発生箇所はランダムです。
- 良いイベント:遭遇したエージェントの才能に比例して資産が2倍になる。
- 悪いイベント:資産の半分を失う。才能に関わらず全員に等しく直撃。
- 条件①:盤上でエージェントは移動せず、イベントがランダムに移動する。
- 条件②:各タイムステップ(1年ごと)にイベントが盤面上に出現する。
この設定は、人生におけるチャンスや不運が、予測不可能なタイミングで訪れる現実の不確実性をモデル化しています。
才能の分布
- 各エージェント(合計1,000人)の才能値は、
平均値:0.6、標準偏差:0.1 の正規分布で割り当てられます。 - 才能値の範囲は0~1の連続値ですが、実際はほとんどが 0.3~0.9 に分布します。
| 才能ランク | 才能値 | 分布の目安 | 人数(1000人中) |
|---|---|---|---|
| 上位層 | 0.75~1.00 | 約2.5% | 約25人 |
| 中上位層 | 0.65~0.75 | 約16% | 約160人 |
| 中位層 | 0.55~0.65 | 約45% | 約450人 |
| 中下位層 | 0.45~0.55 | 約27% | 約270人 |
| 下位層 | 0.00~0.45 | 約9.5% | 約95人 |
 新野くん
新野くん才能値の幅が小さいように感じるんだけど、実社会ではもっと極端じゃない?
 くろひつじ
くろひつじそうだね。あくまでも研究だから、この結果を実社会の能力値格差に置き換えて考えてみると良いよ。
シミュレーション回数
本研究では運の揺らぎ(ノイズ)を防ぐ目的で、合計100回の独立したシミュレーションを実施しています。
各回数ごとに1,000人のエージェントを初期化し、モデル設定は共通にしています。
研究結果
成功者上位10人の才能値
| 順位 | 才能値(100回平均) |
|---|---|
| 1位 | 0.61 |
| 2位 | 0.62 |
| 3位 | 0.60 |
| 4位 | 0.59 |
| 5位 | 0.60 |
| 6位 | 0.63 |
| 7位 | 0.58 |
| 8位 | 0.60 |
| 9位 | 0.57 |
| 10位 | 0.64 |
一見すると才能値の高い人が上位を占めると思われましたが、『才能上位層』より『才能中位層+幸運』に恵まれた者が成功する結果になりました。
この才能中位層とは、エージェント1,000人のボリュームゾーンになります。
資産格差の数値
| 順位(グループ毎) | 資産額(100回平均) |
|---|---|
| 1位 | 2,560~最大40,960ユニット |
| 上位10人 | 200~300ユニット(推定値) |
| 全体平均 | 35ユニット |
| 中央値 | 20ユニット(推定値) |
| 最下位 | 破産(0ユニット) |
初期資産は全員10ユニットからスタートしており、成功者は40年間で資産が約数百~数千倍以上に増加しています。
今回は才能値が0~1のシミュレーションでしたが、実社会の知能格差を反映すると、この格差はもっと広がると考えられます。
パレートの法則との関連性

19世紀にイタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが、様々な国や時期の国民所得配分について調査したところ『人口の20%が、富の80%を所有している』ことを発見したことに由来する法則です。別名8対2の法則とも呼ばれます。
本シュミレーションにおいても、成功者上位20%が資産全体の約80%を占めるような成果配分が観測されました。
成功者の特徴
才能は中位層より少し上位に位置する0.61前後の者が、『運の良いイベント』に遭遇し、資産は指数関数的に増加。『運の悪いイベント』への遭遇はほとんどありませんでした。
そして成功者トップ10の中に、才能トップ10%の人が含まれた回数は25/100回。才能トップ(最高値)の人が成功者トップ10に入った回数はわずか1/100 回でした。
これにより、実社会における有名起業家や芸能人の成功ストーリーを『再現性のある教科書』として信じすぎないことが重要であると言えます。
結論
成功者の多くが才能値中位層の下位ではなかったことから、才能と成功の間には確かに相関関係はあるものの、その関係性は一般に考えられているよりも弱いものでした。
『才能差があまりないのに成功差が極端に広がる』という点を数値で裏付けるのがこのシミュレーションの核心の1つであり、この状況が『運の増幅効果』の強力さを裏付けています。
つまり、才能が突出していても、運に恵まれなければほぼ成功できないという構造が明示されています。
運を手にする方法
さて、次に本研究のモデル設定と実社会における相違点を見ていきましょう。代表的なのは以下の2点です。
- エージェントの行動量を設定していない。
- 実社会では『悪いイベント』遭遇による不利益はコントロールできる。
 くろひつじ
くろひつじこの2点を意識することが、同時に『運を手にする方法』とも関係するんだ。
本研究では、純粋に「運と才能」だけが成功にどう影響するかを測るため、行動・環境選択などの変数を意図的に排除しています。
よってエージェントは、才能値に関わらず『固定位置』におり行動しません。
行動量と適正なリスク
一方で、実社会における行動量はイベントへの遭遇率に直結します。
そして悪いイベントは『適正なリスク』を意識することで、その不利益をコントロールすることができます。
これを実社会での成功に置き換えると、以下のように言い換えることができるのです。
- 『運の良いイベント』…商売の成功
- 『運の悪いイベント』…商売の失敗(投資額や固定費はコントロール可能)
- 『運への遭遇率』…商品やサービスの販促量(不特定多数向けに訴求)
令和の現代、商売の販促方法は様々な手法がありますが、これらの要素を全て満たすのは『Webマーケティング』です。
Webマーケティングについては以下のブログでご紹介しておりますので、ぜひ合わせてお読みください。
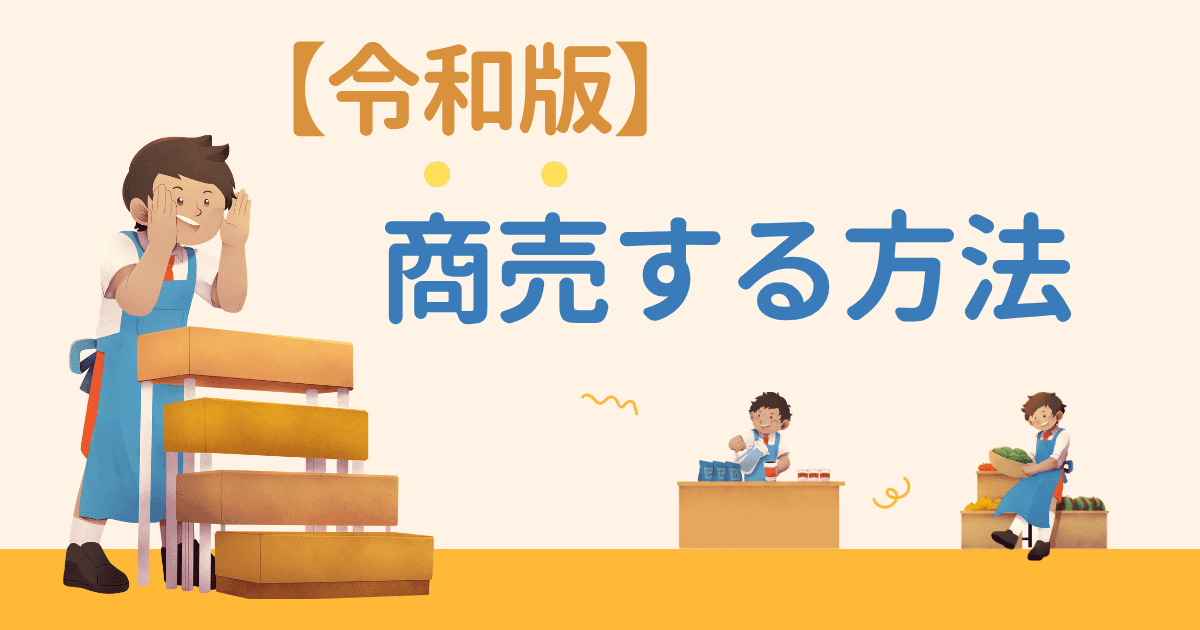
最後に
今回は本研究テーマを基に、成功に必要な「運と才能」それぞれの比重の違いや、運を呼び寄せる『行動量』の重要性についてご紹介しました。
成功には『行動量』が最も重要な要素であり、もし結果が上手くいかなかったとしても「自分がダメだったからだ」と自責し過ぎる必要はありません。
過去の成功者は行動の中で“運の巡り合わせ”を経験しており、そこに至るまで諦めない経験こそが再現性のある成功談と言えるのだと思います。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。