公正取引におけるコンプライランス上、B2B取引をしている会社では、相見積は日常的に行なっています。私は現役で商社の営業マンをしていますが、会社の先輩や同僚の中には、同じ土俵に立った相見積で負けたことがない人がいます。
そんな方々は、どのような方法で勝っているのでしょうか。それは単純に、仕入価格ギリギリを攻めて安い価格で出しているわけではありません。今回は相見積の概要から、実践の場で勝つためのノウハウをご紹介します。
見積の概要
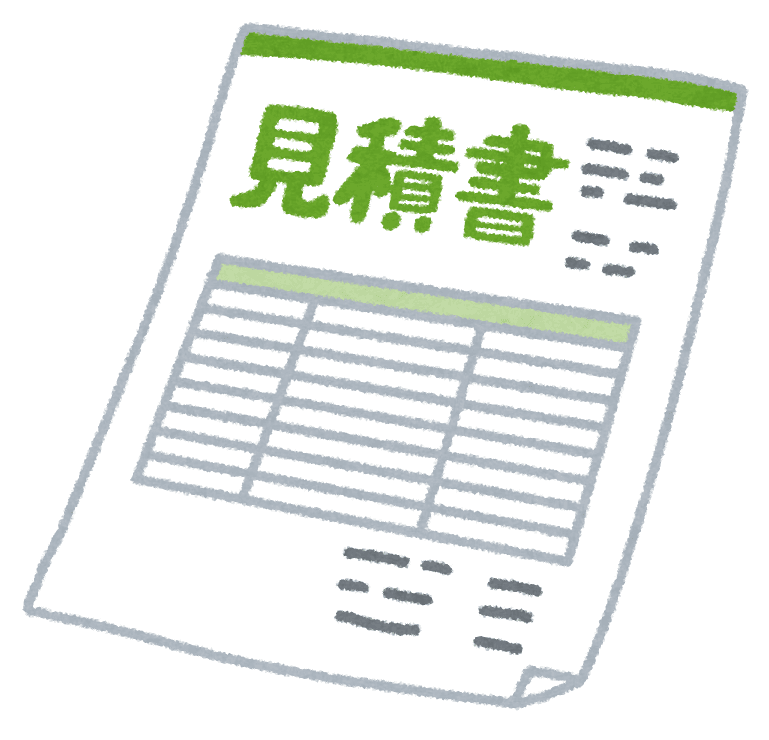
見積には、競合のいる相見積と、競合のいない一社選定の2種類があります。
相見積
複数の会社で同じ仕様の見積を提出し、その価格差で依頼先を決めます。相見積をする会社の数は、得意先の規模にもよりますが、一般的に0~数百万円の案件は2社、1000万円以上となると3社になる場合もあります。
依頼先へ要求する仕様内容は共通で、仕様を満たさなければ競合先とは認められません。商社では競合先に選ばれることを土俵に乗ると表現します。イメージは相撲における土俵と同じです。
異なる商社が同じメーカーで相見積をする場合もあれば、異なる商社が異なるメーカーで相見積する場合もあります。但し、前者はメーカー側が複数の商社へ見積を提出することを了承する場合に限定されます。
相見積の一般的な流れは以下の通りです。
得意先の担当者が商社へ見積依頼をします。商社は依頼を受けたら、依頼内容や仕様書をメーカーへ展開します。商社は自社に商流のあるところからメーカーを選定する場合もあれば、そもそも得意先からメーカー指定がある場合もあります。
要求仕様は総じて複雑な為、仕様書に対し質問点が出たり、漠然とした表現になっていたりする場合が多々あります。その為、Webや面直などで3社(得意先、商社、メーカー)で要求仕様の擦り合わせを行います。商社はこれをキックオフMTと呼びます。
商社から得意先の担当者へ見積を提出します。担当者は自社の承認を得た後、購買部門に見積を上げます。相見積の場合、担当者はこの流れを競合の数だけそれぞれで行う必要があります。
すべての商社から見積が揃った段階で、購買は商社へ入札見積の提出を依頼します。入札見積は公平性の観点から、郵送で、かつ未開封のものでしか認められません。入札見積が揃ったら、購買は各社の見積を同時に開封し依頼先を決定します。
入札見積とは?
入札見積とは、担当者へ提出した見積から値引きをした見積書を指します。入札は安い方に依頼先が決定する為、商社は取りたい案件程より多く値引きします。当然ながら、各社がいくら値引きしたかは開封するまで分かりません。
一社選定
一社選定とは、上述したステップの競合がいないパターンで、得意先の購買は入札見積は依頼せず最終見積の提出を商社へ依頼します。競合がいない一社選定は以下の条件に該当する必要があります。
- 既に導入済みの商品・サービスと同等のものを依頼する場合。
- 既に導入済みの商品・サービスの修理、改善、改造、かつ他社では実施不可の場合。
- 上記いずれかに該当し、かつメーカーが導入時に仲介した商社にしか見積を出さない場合。
つまり、他のメーカーでは要求仕様を満たせない場合、かつそのメーカーが導入時の商社にしか見積を出さない場合は一社選定となります。
商社やメーカーはすべての案件が相見積になってしまうと、十分な利益を出せません。しかし導入した商品やサービスに関する情報を開示しなければ、更新、修理、改善、改造が必要な際は一社選定にすることができます。
よって、多くのメーカーは自社の商品やサービスに関する情報は開示せず、かつ商流のある商社にしか見積を出しません。商流については以下のブログでご紹介していますので、ぜひ合わせてご参考ください。

相見積に勝つ方法
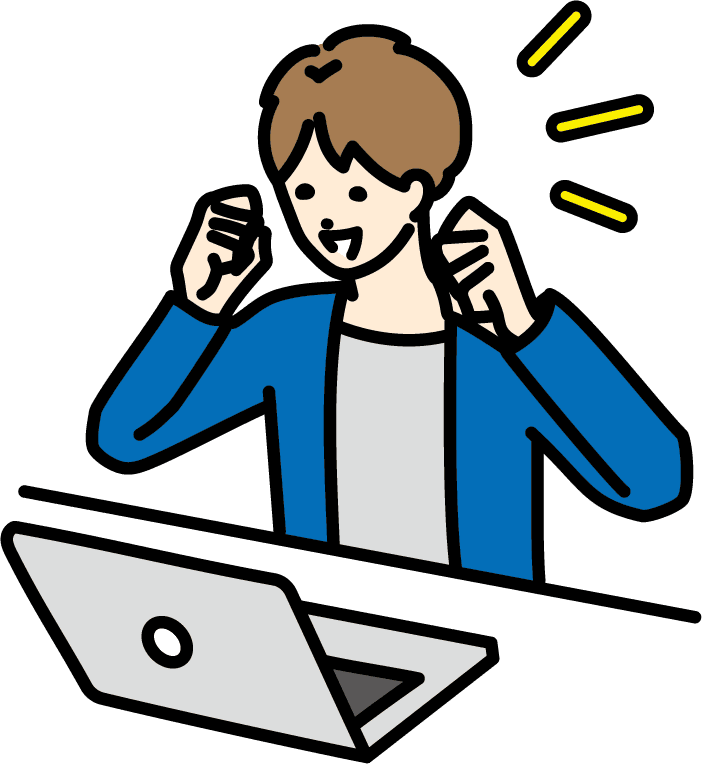
次に、商社が相見積に勝つ方法についてご紹介します。営業も人間なので個人の特性は異なりますが、方法の多様性は無いので以下でご紹介するいずれかの方法を使っています。
競合に当見積を依頼する
得意先から見積依頼を受けたら、商社は必ず競合先の情報をヒヤリングします。これは競合先が自社と関連がある場合、当て見積を提出してもらえる可能性を探る、もしくは競合先の相場を調査するのが目的です。
普段から競合との関係を密に取っている営業は、あえて当て見積を出したり、また当て見積を依頼することがあります。しかし公正取引上、この方法は禁止されています。
当て見積とは?
当て見積とは、その案件を受注するつもりがなく競合より高い金額の見積を提出することを指します。当て見積を提出する状況は以下いずれかの場合になります。
- 依頼を受けた商社やメーカーがその案件を取る気がない、かつ辞退できない場合。
- 既に依頼先は決まっているが、公正取引上相見積をしなければいけない状況で、得意先やメーカーから当て見積の提出を依頼された場合。
仕様検討段階で他の競合を外す
得意先と商社の間で信頼関係ができている場合や、仕様検討に必要な材料を商社が持っている場合、見積依頼前の仕様検討段階で商社が介入することがあります。
この場合、要求仕様に他社が再現不可能な内容を盛り込んだり、商社が開示した情報に対して関係者社外秘とすることで、競合が参入できなくすることができます。
特に現場思考の営業マンは、得意先の担当者より現場のニーズを理解してしまう場合があり、この状況に出くわすことがあります。
受注後の仕事を担う前提で他の競合を外す
前述した通り、得意先の担当者は競合の数だけ見積依頼、仕様打合せをする必要があります。さらに要求仕様を満たせない内容があれば、依頼先を再検討する必要もあります。
そこで依頼先を1社に絞る代わりに、得意先がするべき受注後の仕事もその商社に一任する場合があります。これは商社がそれを提案する必要があり、かつその商社に対する信頼関係が既に構築されている場合に限られます。
相手が確実に勝てない価格で見積する
商社は物件毎に5%~20%程の粗利益を確保しています。他の物件の粗利益が20%のところ、例えば5%で受注し残りの15%を入札案件に充てれば、そこには要求仕様以外の要因による差額が生まれます。
但しこれを受注すれば得意先のデータに受注実績として残る為、後々リピート案件がきた際自分を苦しめるリスクがあります。よって、事前に競合の価格調査を行う前提の方法となります。
またこれは公正取引の観点から認められる方法ではなく、監査で指摘される可能性があります。但しその監査員は自社の商品やサービスの専門家ではない為、受注履歴から違和感を見つけ出すことは難しいのが実態です。
メーカーへ他の商社に見積を出さないよう依頼する
メーカーが同じで商社が異なる案件の場合、予めメーカーへ他の商社に見積を出さないよう依頼したり、定価で出してもらうことがあります。しかし、この方法はメーカーとの信頼関係がある前提条件が必要です。
十分な信頼関係があれば、メーカー側から得意先へ向けて、商社を指定してもらえることもあります。
まとめ
以上のことから、見積に勝つ為には以下いずれかの条件が必要となります。
得意先やメーカーと信頼関係を構築している
得意先やメーカーとの信頼関係を築いていたり、もしくは両社に発生する仕事を削減できるスキルがあれば、これが結果として競合先を外す交渉や一社選定の案件獲得に繋げることができます。
既に十分な営業成績を持っている
既に受注物件数や相応の利益がある場合、その金額を他の入札案件に充てることができます。営業成績が不十分な場合は受注段階のコントロールができず、かつ追加費用にも柔軟に対応することが難しくなります。
最後に
優秀な営業マンは、より多くの仕事を獲得できるようになります。その理由は、そもそも相見積に勝つ為には信頼関係と普段からの受注金額が必要で、受注が受注を呼ぶ好循環が生まれやすいことにあります。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。




