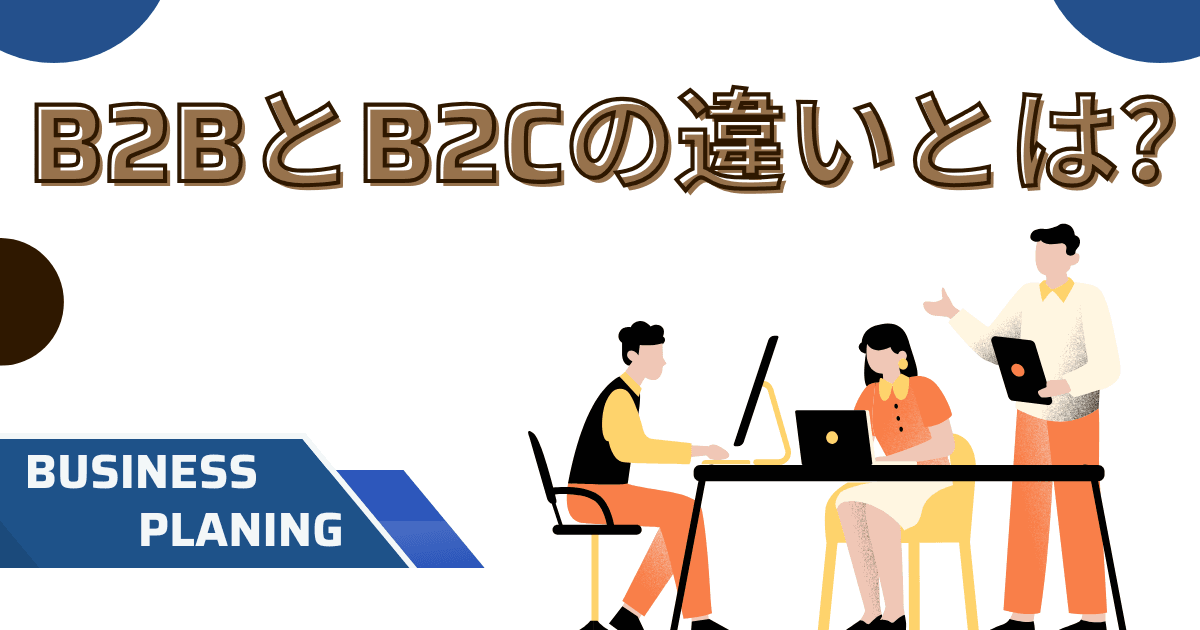私は商社においてB2Bの法人営業をしています。過去にB2Cの営業も経験していますが、現職であるB2Bの方が売上・粗利益ともに圧倒的に高く、かつ労力も少ない体感です。
では実際に、B2BとB2Cで市場規模はどのくらい差があるのでしょうか。今回はそれぞれの業界における市場規模から、参入している会社の数、売上に対する労力の比較をご紹介します。

- 参入業界に迷っているスタートアップ経営者
- 転職先の業界に悩んでいるビジネスマン
- 新規事業を任されているリーダー
 新野くん
新野くん世の中には会社がいっぱいあるけど、市場規模を比較すれば稼ぎやすいか稼ぎにくいかが分かるのかな?
 くろひつじ
くろひつじメン!そうだね。B2B、B2Cそれぞれの市場規模と参入している競合の数を見てみれば、少なくとも稼げにくい業界はわかるんだ。
起業・もしくは転職先の業界を選ぶ中で、よく例として会社員を定年後、退職金でカフェを開くおじさんが揶揄されます。
カフェを含む飲食業界は一般的にB2Cに当たる商売で、労働集約型のビジネスモデルとなります。この分類は多くの場合、稼ぐことは愚か継続することすら難しいとされています。
但しどの業界やビジネスモデルも、簡単に稼けるものはありません。その前提の基、あくまで統計情報から客観的な視点でおすすめの参入業界をご紹介できればと思います。
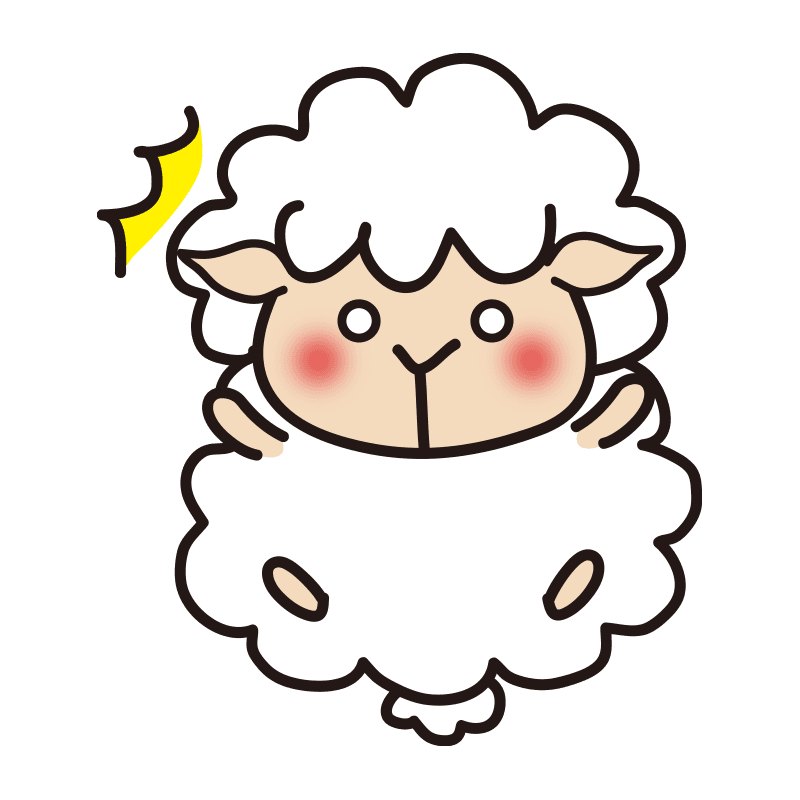
- 宿泊・飲食業は1社当たりの粗利益が最も低く、人件費率が最も高い。
- 情報通信業は1社当たりの粗利益が最も高い。しかし人件費率も比較的高め。
- 製造業は統計上最も魅力的な業界だが、一部の会社に偏りがある為中央値を見る必要がある。
B2B B2Cとは?
B2B
企業と企業の取引を指します。

B2C
企業と消費者の取引を指します。

統計情報

日本におけるB2B及びB2Cそれぞれの市場規模と会社の数を比べてみましょう。市場規模とは、単純にその業界の取引金額を示します。これを会社の数と割り算すると、平均値から想定される概算の売上見込みを割り出せます。
総務省統計局の「令和3年経済センサス‐活動調査」および経済産業省の「2023年経済産業省企業活動基本調査(2022年度実績)」に基づいて、日本における各業界の企業数と市場規模を見てみましょう。
B2Bの業界
| 業種 | 企業数 | 市場規模 | 平均粗利率 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 約33.9万社 | 約387兆円 | 41.8% |
| 建設業 | 約42.6万社 | 約120兆円 | 20% |
| 卸売業 | 約74.1万社 | 約480兆円 | 10% |
| 情報通信業 | 約5.7万社 | 約75兆円 | 45% |
B2Cの業界
| 業種 | 企業数 | 市場規模 | 平均粗利率 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 約74.1万社 | 約480兆円 | 27.6% |
| 宿泊・飲食業 | 約42.7万社 | 約21兆円 | 65% |
| サービス・娯楽業 | 約31.4万社 | 約30兆円 | 50% |
| 医療・福祉 | 約33.0万社 | 約173兆円 | 30% |
一社当たりの指標

次に、前述した指標を基に1社当たりの粗利益の平均値を割り出します。この粗利益と労働集約性である人件費率を比較すれば、統計上の稼ぎやすい業界と稼ぎにくい業界を見ることができます。
人件費率とは?
人件費率とは、売上高に対する人件費の割合を示す数値です。計算式は人件費 ÷ 売上高×100=人件費率となります。人件費には、従業員や役員への給与や賞与・法定福利費・法定時間外労働割増賃金・退職金・福利厚生費・人材採用や教育費などが含まれます。
B2Bの業界
| 業種 | 売上高(単位:百万円) | 粗利益(単位:千円) | 人件費率 |
|---|---|---|---|
| 製造業 | 1,142 | 477,186 | 7.3% |
| 建設業 | 282 | 56,338 | 8.9% |
| 卸売業 | 648 | 64,777 | 5.9% |
| 情報通信業 | 1.316 | 592,105 | 19.3% |
B2Cの業界
| 業種 | 売上高(単位:百万円) | 粗利益(単位:千円) | 人件費率 |
|---|---|---|---|
| 小売業 | 648 | 178,785 | 11.6% |
| 宿泊・飲食業 | 49 | 31,967 | 25.5% |
| サービス・娯楽業 | 96 | 47,771 | 13.8% |
| 医療・福祉 | 524 | 157,273 | 20.4% |
参考文献:マネーフォワード
まとめ
1社当たりの粗利益が最も高いのは情報通信業という結果になりました。全体的にB2Bの業界は粗利益が高く、また労働集約性も低い業界であることがわかります。
また、宿泊・飲食業は最も粗利益が低く、最も人件費率も高い業界となりました。この業界へ参入するには、相応の資金力か差別化できる強みが必要でしょう。
尚、この統計はあくまで平均値から割り出した情報となり、特に製造業においては一部の会社に偏りがあることは考慮する必要があります。
自社で業界ごとに正確な統計を導き出す場合、中央値から算出することをおすすめします。
相違点

ここまではそれぞれの業界の統計情報をご紹介しましたが、参入業界を選ぶ上では、市場規模だけではなく自分(自社)の強みを活かせるかも重要になります。
ここからは、B2BとB2Cそれぞれの特徴をご紹介します。特徴とマッチする強みを活かせば、市場規模が小さい業界であっても大きな成果を期待できるでしょう。
制作品と既製品の比率
B2BとB2Cの相違点として、まず取り扱う商品の違いが挙げられます。一般的に、B2B取引では顧客の要求する仕様に応じたオーダーメイドの制作品(受注生産品)が多く提供されます。
一方、B2C取引では広範な消費者市場を対象とした大量生産の既製品が主流となります。近年ではB2Cにおいても、高所得者向けにオーダーメイド品を取り扱う傾向はありますが、それも一部に限られています。
商品やサービスの単価
B2B取引では取引先が法人であるため、1件あたりの取引額は大きくなることが一般的です。一方、B2Cでは単価の低い商品が中心であり、多くの消費者を対象とし取引量を増やすことが収益拡大の鍵となります。
これにより、薄利多売のビジネスモデルが難しい中小企業は、B2Bのビジネスを行うことが多い傾向があります。
顧客との関係性
B2Bにおける取引では、顧客との関係は長期間に及ぶケースが多いです。対してB2Cは不特定多数のユーザーに対して短期で関係性を持つか、またそもそも関係性を持たないケースも多くあります。
まとめ
| 項目 | B2B(企業間取引) | B2C(企業対消費者取引) |
|---|---|---|
| 顧客 | 法人(企業) | 一般消費者 |
| 購買プロセス | 複雑で長期間(複数人の意思決定) | 短期間(個人が意思決定) |
| 購買目的 | 事業運営・利益追求 | 個人の生活向上・娯楽 |
| 取引単価 | 高額(1件の契約が大きい) | 低額(個々の取引金額は小さい) |
| 取引頻度 | 長期的な継続取引(契約ベース) | 短期的な取引が多い |
| 販売数 | 少量の大口注文 | 大量の小口注文 |
| 価格設定 | 顧客ごとの個別交渉(柔軟な価格調整) | 固定価格(定価販売が主流) |
| マーケティング手法 | 直接営業、カスタマーリレーション重視 | 広告・SNS・Eコマースなどの大衆向け施策 |
| 意思決定者 | 企業の購買部門・経営層など複数 | 個人 |
| 購入リスク | 高い(事業戦略に影響) | 比較的低い(返品や交換が容易) |
| ブランドロイヤルティ | 長期的な関係重視(信頼が重要) | ブランドの好みや流行が影響 |
| カスタマイズ度 | 高い(仕様変更やオーダーメイド可能) | 低い(大量生産品が主流) |
最後に
今回はB2BとB2Cの違いをテーマに、統計情報からそれぞれの特徴をご紹介しました。
会社は参入業界を決める上で、市場調査から自社のビジネスモデルを想定し、顧客のターゲティングを行った上で商品やサービスの訴求プランを立てます。ぜひ今回ご紹介した内容を検討材料の一つとして頂ければと思います。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。