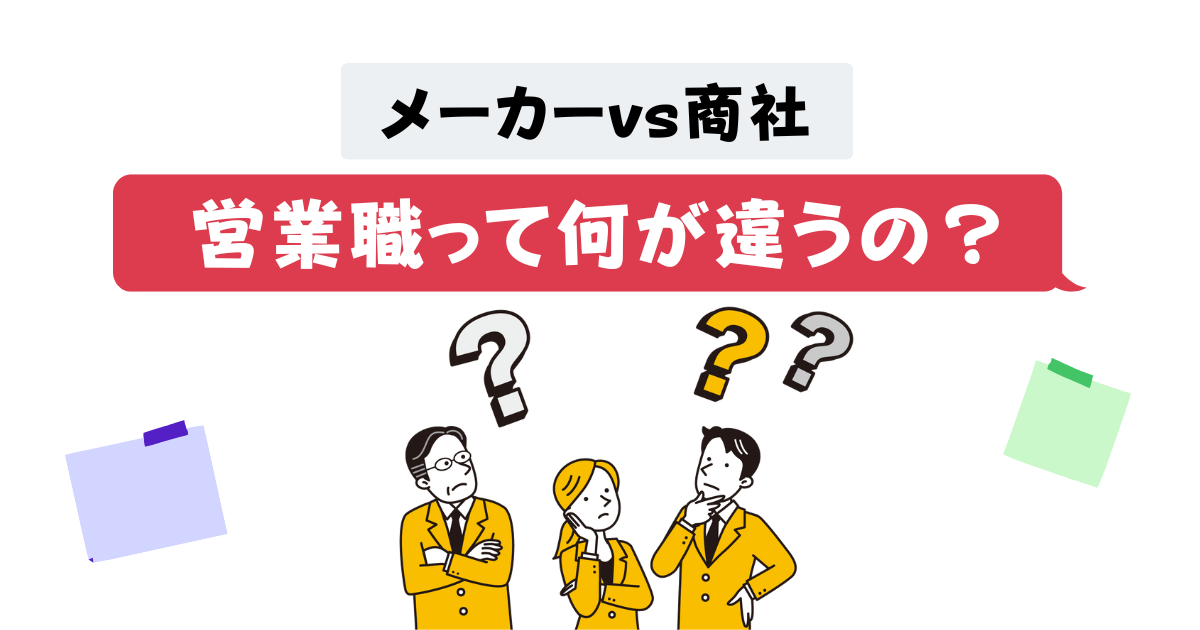私は現役で商社の営業マンをしています。
商社の営業職とメーカーの営業職には、年収水準から日々の業務内容まで多くの違いがあります。
今回は、『商社の営業職とメーカーの営業職の違い』をテーマとし、それぞれの年収や業務内容について具体的にご紹介します。

- 営業職に就きたい人
- 待遇や業務内容に不満がある人
年収の比較
商社の営業職は、一般にメーカーの営業職より給与水準が高い傾向があります。
メーカーは自社工場における商品在庫費や設備維持費などの固定費が大きく、利益を人件費に振り分けにくい一方で、商社は資源権益や右左品のトレードで稼ぐ変動費が主なコストになるためです。


一時的な不景気による利益の減少があった際、固定費は会社経営に大きな打撃をもたらすため、メーカーは「労働法上一度上げたら下げにくい」正社員の基本給(人件費)はなるべく上げたがらないのです。

商社用語の右左品とは、顧客から発注された後にメーカーへ発注する商品を指します。対義語は在庫品であり、自社で在庫を持たず右から左へ流すことから「流れモノ」または「右左品」と呼ばれます。
商社の平均年収
五大商社の平均年収は1,857万円
上場専門商社8社の平均年収は約973万円
Bloomberg社によると、2025年3月期の五大商社の平均年収は以下となります。
- 三菱商事 2,033万円
- 三井物産 1,996万円
- 伊藤忠商事 1,805万円
- 住友商事 1,744万円
- 丸紅 1,708万円
また2025年3月期、有価証券報告書やIR BANKなどに記載の上場専門商社8社の平均年収は以下となります。
メーカーの平均年収
上場メーカー代表8社の平均年収は約822万円
OpenWorkなどに記載の上場メーカー8社の平均年収は以下となります。
会社選びの重要性
しかし、年収を最重視する場合は「どの業界にするか」よりも「どこの会社にするか」の方が重要です。
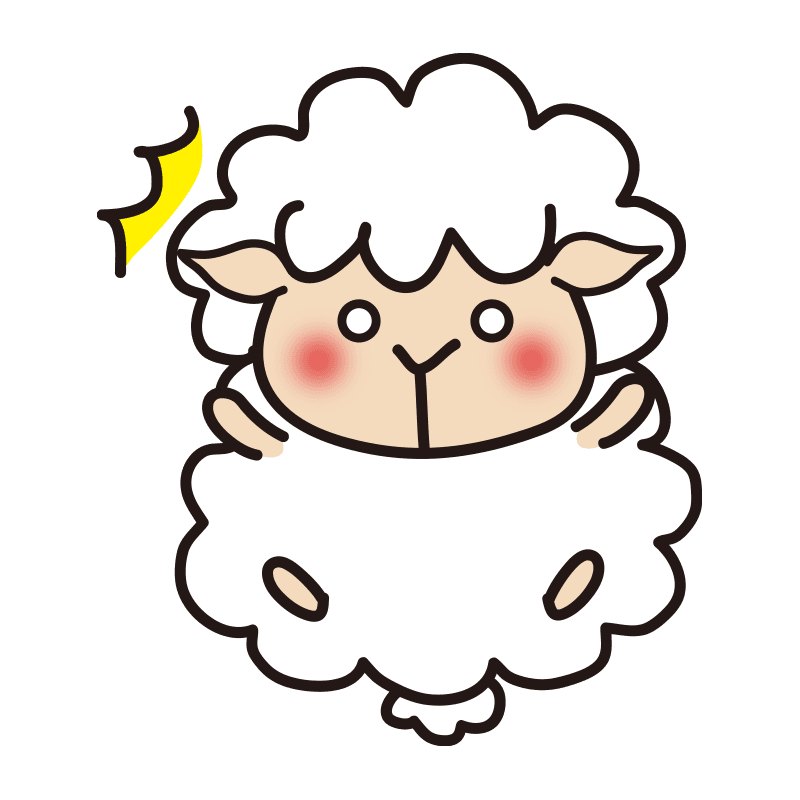
大手転職サイトdudaによれば、総合商社・専門商社・メーカーそれぞれの平均年収はほぼ同一水準になります。



duda社は登録者ベースで平均年収が算出されており、若い年齢層やベンチャー・中小企業を含むため、一般的なイメージより平均水準が低くなる傾向にあるのです。
業務内容の比較
商社もメーカーも、国内外問わず複数の顧客のプロジェクトを並行して進めます。
しかし大きな相違点として、メーカーの営業職が顧客へPRする商材は、自社製品(またはOEM製品)に限られますが、商社がPRする商材は取引先の他社製品であり、その数に制限はありません。
プロジェクトの役割
よって、商社とメーカーでは顧客のプロジェクトにおける役割が異なります。
通常、顧客のプロジェクトは複数メーカーが関与しますが、日本では「餅は餅屋理論」の文化があり、特定のメーカーが自社と関連がないメーカーの取りまとめをすることはありません。
その一方で、商社は取り扱うメーカーに制限がないため、顧客の要望次第でプロジェクトそのものを担い、各メーカーを指揮する立場に立つことがあります。


よって、どちらかと言うと商社の方が、より顧客に近い立場でプロジェクトを進める機会が多くなります。
 くろひつじ
くろひつじ対してメーカーの営業職は、自社商材のスペシャリストとして、プロジェクトにおける特定の分野だけを担うんだ。



メーカーの営業職は「狭く深く」商社の営業職は「広く浅く」って感じなんだね。浅いわけではないけど、専門性は各メーカーの力を借りる意味で。


餅は餅屋とは、「どんな物事でも、その道の専門家に任せるのが一番良い」という意味のことわざです。ビジネスでは、自社で全てをこなそうとするのではなく、専門外のことは外部業者に外注する方が効率的で、かつ最終的な利益が上がるという意味で使われます。
責任範囲と板挟み
商社の営業職は、プロジェクトにより複数のメーカーと関与するため、取引先の数・売上の規模・それに伴う責任範囲すベてが大きくなります。
また、商社はメーカーの営業職ほど商材に関する専門性がないため、状況次第で顧客・メーカーそれぞれへ協力を仰ぐことも多々あります。
しかし、顧客とメーカーの関係性や担当営業次第によって、各社の連携が取りづらく、板挟みになるケースも少なくありません。


営業職最大のストレス要因である板挟みは、メーカーの営業職は2社間(顧客・自社)で起こりますが、商社の場合は3社間(顧客・メーカー・自社)になるのです。
板挟みされる相手が多いほど、当然ながら受けるストレスも大きくなります。
付加価値の比較
ビジネスにおける粗利率は、付与する付加価値の大きさに比例します。
商社は売上規模が巨大である反面、生産者ではない特性上、平均粗利率は一桁台から10%前後と低めです。
一方で、メーカーは業界によって差はあるものの、平均粗利率は20%前後と高くなります。(自動車業界で約15~20%、電子機器で約20~30%)



メーカーの付加価値は、提供する商品やサービスだよね。商社の付加価値って何があるの?



実業務では、取引に関する雑務(通関・貿易・在庫管理・情報共有)が主だけど、最も大きな付加価値は、与信関連だね!
与信取引
商社は、取引先に対して””銀行“”のような『代金回収や商材に対する信用・保証』を提供します。
企業間取引における「検収条件」や「支払い条件」は、その取引ごとに双方で取り決めし、仕様書や注文書に記載する義務があります。
しかし、それらの条件が同意を得られず、例え必要な商材でも取引に至らないケースも珍しくありません。


顧客がメーカーへ支払いOKとする条件(基準)を指します。有形物の場合、商材が出荷した時点で条件を満たす「出荷基準」。無形物の場合、顧客の定めた条件で満たす「検収基準」が一般的です。
例えば建設業界は、重層下請け構造により、メーカーも外注先への支払い義務が生じます。この外注への支払いが顧客からの支払いより早い場合、メーカー(下図でいう”下請”)は黒字倒産するリスクが上がるのです。


この状況を回避できるのが商社や仲介業者であり、顧客・メーカーとの支払い条件の調整(立替払い)や、商品の不具合による支払い延長の了承(品質保証)、また場合により追加費用の支払いも行います。
与信管理
企業間取引では取引口座開設前に、必ず相手企業の「与信管理」を行います。
与信管理とは、取引先の倒産リスクを最小限に抑えるため、取引開始前に会社情報(法人名、法人番号/登記情報、設立年月、事業内容、資本金、従業員数など)を調査することを指します。
商社は取引自体を仲介するため、この与信管理を代行してくれる役割を持ちます。特に「資金繰り」や「情報」に強い商社は、この特性が好まれるのです。


例えば金額の大きい設備を制作途中に、
- 顧客が倒産した場合…それまで制作した代金を回収できないリスクが生じます。
- メーカーが倒産した場合…代替え品の選定、指定納期調整などのタスクが生じます。
最後に
今回は、『商社の営業職とメーカーの営業職の違い』をテーマとし、それぞれの年収や業務内容について具体的にご紹介しました。
なお、商社の付加価値は以下のブログでご紹介しておりますので、ぜひ合わせてお読みください。


今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。