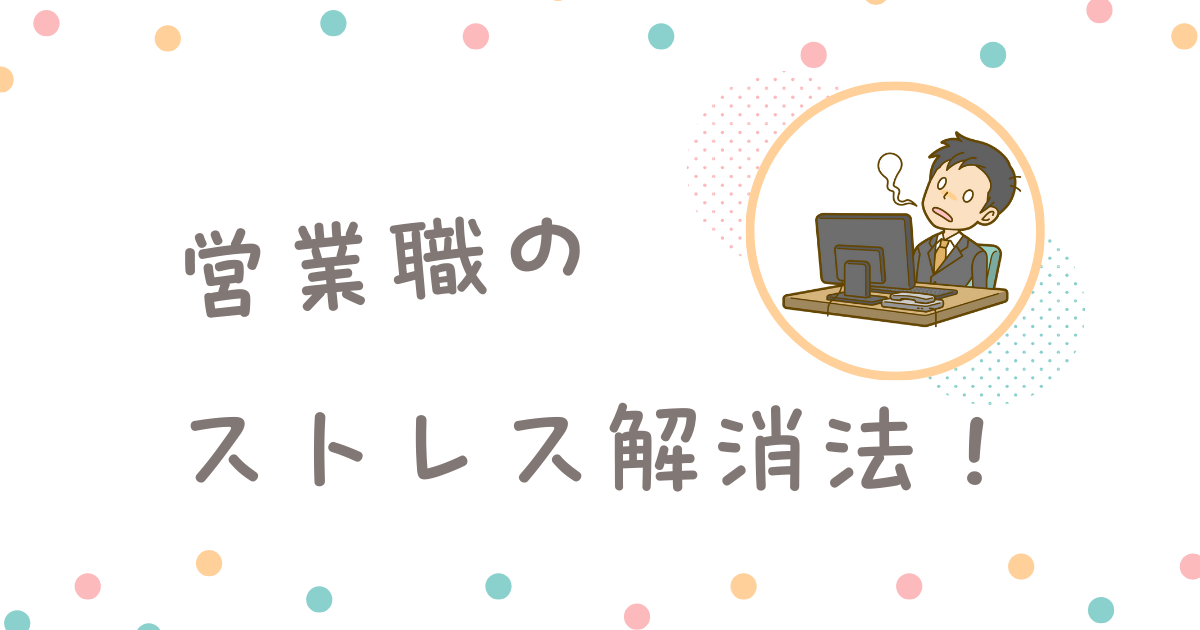私は現役で商社の営業マンをしています。
営業は会社間(顧客・取引先・自社)の板挟みや、ノルマ達成へのプレッシャーにより、非常にストレスの多い職種です。
今回は、実際に営業をしている経験から、営業職のストレス解消法についてご紹介します。

- 嫌なことを忘れられずにいる人
 新野くん
新野くん顧客に謝罪に行った日は、その後1週間くらい時々思い出しては落ち込んだりイライラしちゃうんだよね。。



飯の代わりにストレス食ってるような新野くんでもそうなるんだね。営業のストレスは避けようがないから、普段から溜め込まないことが重要だよ。
営業が謝罪する場面の多くは、「自分自身の原因」ではなく「組織上の原因」です。
日常的に、かつ自分がコントロールできない要因でプレッシャーやストレスに晒されるため、営業はメンタルを強く保たないといけない職種なのです。
尚、今回も個人の独断と偏見を含みますので、酔った商社マンの話に付き合ってる気分で、気軽にお読みください。
はじめに
本ブログでご紹介するストレス解消法は、『自分がコントロールできる』領域に限定しています。
ストレスの要因は必ず「他人」が関与しており、他人は「変わること」はできても「変えること」は不可能だからです。
夜は寝る
O:社が行った調査では、最も睡眠時間が少ない職種は『営業職』との結果でした。
実際に私の周りで働いている営業も、夜に眠らない(眠れない)人は多くいます。


そして、人間は昼よりも夜のほうがネガティブな思考に囚われやすいと言われますが、これは心理学・神経科学の領域からも裏付けられています。
概日リズムと思考パターンの関係性
24時間の概日リズムに応じて、人間の思考傾向は変化します。
イギリスのブリストル大学がTwitter約8億件の投稿を分析したところ、朝方は実践的で論理的な言葉が多い一方、『夜になるほど感情的(悲観的)な方向に傾く』ことが明らかになっています。
脳の疲労と反芻思考
この要因は、脳の働きが関係しています。
「理性」を司る前頭前野は日中に活発に働きますが、夜になると疲労によりその働きが低下します。一方で、不安や恐怖などの「情動」を司る扁桃体は、夜間でも活発に機能します。
その結果、昼間なら気に留めないような小さな後悔や嫌な記憶が、夜には必要以上に重大に感じられ、頭の中でぐるぐると繰り返し浮かびやすくなります。


反芻思考(はんすうしこう)とは、過去の出来事や将来の不安など、ネガティブな物事について繰り返し考え続けてしまう思考のことで、別名「ぐるぐる思考」や「抑うつ的反芻」とも呼ばれます。
参考文献:Apparel-Web
昼寝をする


プラス社が行ったアンケート調査によれば、「職場で昼寝をした経験がある」人は全体の70.2%にも上りました。
別の会社であるホンダ社が行った調査でも、「普段から昼寝をする習慣がある」人の割合は78.7%にも上り、全体の半数以上の人が昼寝を習慣にしていることがわかります。
営業職の昼寝
営業職は、良い意味でも悪い意味でも、働く『時間と場所』の融通が効きます。
もし残業や飲み会などで、帰宅時間のコントロールができない場合は、昼寝をする習慣をつけましょう。



仕事の中で時間を捻出するのは大変だけど、昼寝にはそれを凌駕する色んなメリットがあるんだ。



確かに、昼寝は体に良いってよく聞くけど、具体的にどんなメリットがあるの?
昼寝することのメリット
ストレス軽減・気分の安定
昼寝は脳のストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制されるため、心身の緊張が和らいで気分を安定させることができます。
15~30分程度の短い昼寝でも、副交感神経が優位になり深いリラクゼーション状態がもたらされるため、イライラ感や不安感が軽減されるのです。
記憶力・注意力の回復
NASAの研究では、宇宙飛行士やパイロットに26分間の昼寝をとらせたところ、仮眠を取らなかった時と比べて認知能力が34%上昇し、注意力も54%上がったとの報告がされました。
脳は仮眠中にも情報処理を続けるため、昼寝を取り入れることで、その後の学習や問題解決能力の向上が期待できるのです。
健康面への好影響
定期的な昼寝習慣は、長期的な健康にも寄与します。
ギリシャで行われた研究では、「週に3回以上、30分程度の昼寝」をする人は、全く昼寝をしない人に比べて「心臓病による死亡リスクが37%も低下した」ことが報告されています。
参考文献:nishikawa ダイヤモンド・オンライン
運動・筋トレをする


エムエム総研が営業職1,007人を対象にした調査では、約9割の人が、普段から何かしらの運動をしているという結果になりました。
但し、この結果はIT業界(SaaS企業)の営業職に限定したものであり、業界や企業文化によって運動実践率は異なります。
実際に、厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によれば、20~59歳の男性で「運動習慣がある」人の割合は26.4%に留まっています。


運動習慣者の定義
この「運動習慣者」の定義は、「週2回以上、1回30分以上の息がはずむ運動を1年以上継続している者」です。
世界保健機関(WHO)も、健康増進のため成人は週150~300分の中強度有酸素運動と、週2回の筋力トレーニングを組み合わせるよう推奨しています。



個人的な体感だけど、営業職って意外と運動してる人多いよね。



そうだね。一方で外食する機会も多いから、「太ったり痩せたりを繰り返す」人もいるね。
運動することのメリット
一般成人において、定期的な運動は心身の健康に多大なメリットをもたらします。
メンタルヘルスへの影響
運動はセロトニンやドーパミンの分泌を促し、気分を高めてストレスを緩和する効果が報告されています。
また、運動によりストレスホルモンの調節を整え気分を高めることで、不安や抑うつ症状の軽減につながることが研究で示されています。
睡眠の質向上
適度な運動習慣は、夜間の睡眠の質を高め「睡眠障害を和らげる」ことが分かっています。
これは運動により体温リズムや自律神経が整い、夜間にスムーズにリラックス状態へ移行できるためと考えられます。
不眠症の高齢者を対象とした研究では、16週間の中強度の有酸素運動により、自己報告の睡眠の質や、気分が顕著に改善した例があります。
収入の柱を複数持つ
勤務先の給料に依存した生活をすることは、逃げ場のない状態で生活することと同義あり、精神的な苦痛を生むほど危険なことです。



つまり副業ってことだよね。その重要性は理解してるけど、本当にうまくいくのかな?



営業成績と一緒で、商売にも再現性はないよ。軌道に乗るかは別として、その取り組み自体が精神的に良い効果を持つんだ。
副業することの精神的効果
副業を継続することは、その取り組み自体に精神的なメリットがあります。
例え農耕型のジャンルで金銭的な報酬が少なくても、続ければ将来的に必ず上向くという希望が、精神的な会社依存から抜け出せさせてくれるのです。
農耕型の副業とは
副業のジャンルは狩猟型・農耕型に区分されます。
狩猟型の副業は、直接商品やサービスの売買を行うジャンルを指します。
一方で農耕型の副業は、商品やサービスを販売するのではなく、『人を集める』ことを目的とした情報発信を行うジャンルです。
- 狩猟型の副業:せどり、クラウド案件、イベントスタッフ 等
- 農耕型の副業:ブログ、YouTube、SNS、オンラインサロン 等
それぞれの成長直線




農耕型は開始当初の成果が少ないものの、将来的に別ジャンルのビジネスへ移行しやすい特徴があります。
一方で狩猟型は、開始当初の成功体験は得やすいですが、マンパワーでこなせる限界点に達すると成長が止まる可能性があります。
収入源を増やすことの重要性は、以下のブログでご紹介しておりますので、ぜひ合わせてお読みください。


まとめ
ここまでご紹介した内容に共通している点は、時間を作ることです。
従業員にとっての仕事とは『時間を対価に報酬を得ること』であり、資本主義の特性上、その対価(時間)は今後も肥大化し続けます。
特に営業は組織の最前線で商売ができるため、非常にやりがいがあり楽しいものですが、従業員は自分の大切なものを犠牲にするほど成果と報酬は紐づいておりません。
今一度自分の時間に無駄がないかを洗い出し、本当に大切なことに充てる時間を増やすきっかけになれば幸いです。
最後に
今回は、実際に営業をしている経験から、営業職のストレス解消法についてご紹介しました。
今後も現代のビジネスマン向けに情報を発信していきますので、本ブログをブックマークして頂けますと幸いです。